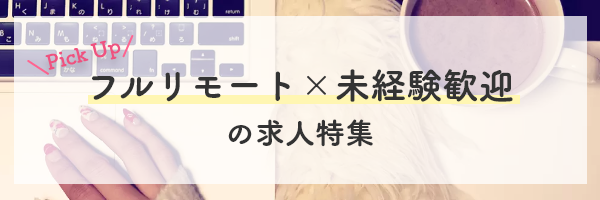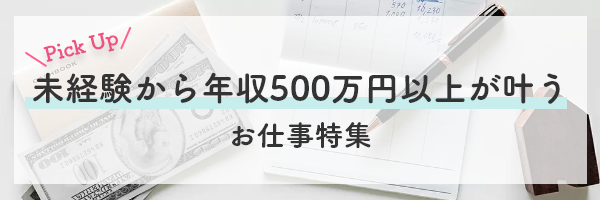アパレル系接客・販売の面接時の服装について
転職面接では、女性もスーツ着用が基本マナーです。しかし、アパレル系販売職の場合は「私服で」と指定があり、応募者や応募者の好むファッションがブランドイメージに合うかどうかをチェックされるケースがあります。「私服」でもあくまでも採用面接というTPOですから、場違いにならず面接官へ好印象を与えなくてはいけません。
そこで、この記事ではアパレル系販売職の転職面接時における服装について解説します。
アパレル系販売職の面接は「私服」の場合が多い
「私服でお越しください」と言われることの多いアパレル系販売職の面接。「私服」=普段着ととらえるのではなく、「面接の服装」として戦略的にコーディネートすることが必要です。なぜなら、面接官は応募者が実際に店舗に立って働く姿を想像して判断するからです。「接客できる清潔感があるか」「そのブランドの雰囲気に合うか」をチェックされていると理解し、適した服装を選びましょう。
服装選びの3つのポイント

ポイント1.清潔感は最も大事!
アパレル系販売職ですから常に店舗で接客しますので、清潔感があって不快感を感じさせない、つまり「店舗に立っても問題ない」「清潔感が重要と知っている」と面接官に感じさせることが最も大切です。しわや汚れがないか、髪や爪の手入れが行き届いているかなども見られています。
また、あくまでも採用面接の場ですから、応募先がギャル系ブランドで露出の多いアイテム展開をしていても、TPOを考えて控えめにしておいた方が無難です。
ポイント2.応募先ブランドのファッション系統に合わせる
アパレル系販売職の面接では、応募先ブランドの系統(ジャンル)を意識したコーディネートがおすすめです。カジュアル系、キレイめ系(コンサバ系)、ガーリー系、ギャル系、モード系など様々な系統がありますので、その雰囲気をしっかり押さえたコーディネートでまとめましょう。
例えば、キレイめ系(コンサバ系)でも年代、雰囲気で細かく分かれていますので、「御社のブランド(系統)が好き」「ブランド(コンセプト)を理解している」と感じさせるように意識しましょう。無理して一式買いそろえる必要はありませんが、応募ブランドの服でコーディネートできればベストで、「最新シーズンのアイテム」を取り入れると面接でも好印象でしょう。
ポイント3.自分自身に似合っていることも重要
自分に似合っている(自分を上手に表現・演出できている)コーディネートかどうかも重要なポイントです。応募先ブランドの服を一部取り入れて、自分なりにアレンジして着こなしをアピールできるとベストですね。
応募先ブランドの服を着ていても「本人の雰囲気に似合っていなくて、全く良さが伝わらない」状態なら逆効果。あなた自身が「似合っているか自信が持てず、面接に集中できない」ことになっては本末転倒です。
ブランド系統に合う(近い)自分の着慣れている服を選ぶ、そのブランドの店舗で販売スタッフに相談して選んでもらうなど、あなた自身の魅力を引き出すことを心掛けましょう。
ブランドで評価が分かれるかもしれないコーディネート
デニムは多くのブランドでOK
カジュアル系ブランドの面接では、デニムは必ずしもNGではありません。もちろん、「ブランドの雰囲気に合うか」どうかと「面接というTPO」を押さえていることが大事ですから、ダメージ加工が強過ぎたり、スタッズなどの装飾が激しいデニムは避けた方が無難といわれます。スキニーやワイドなどさまざまな種類がありますが、トレンドやトータルコーディネートとして面接シーンに適しているかどうかで判断しましょう。
もちろん企業によってはデニムはビジネスシーンにふさわしくないと考える場合もあるので、求人情報や面接情報から読み取る必要はあります。
トレンドの取り入れ具合は応募先ブランドに合わせる
アパレル系販売職ですから、トレンドを押さえていることは評価されますし、センスもアピールポイントのひとつになります。
ただし、スーツブランドやオフィスファッションのブランドでは、評価が分かれる可能性もあります。迷うなら無難な方を選びましょう。
面接時に避けるべき服装
リクルートスーツ(スーツ)
「私服でお越しください」と言われているのに、リクルートスーツで臨むのはNGです。ただし、リクルートスーツではなくこなれ感のあるスーツなら、大人向けのキレイめ系ブランドなら許容されるかもしれません。「ブランドのコンセプトが理解できている」と服装から伝わることが重要です。
ジャケットも必須ではありませんので、不自然なファッションになるくらいなら無理に着用しなくても大丈夫です。
競合他社のロゴ&ハイブランド
同じファッション系統でうまくコーディネートしたとしても、競合他社のロゴが見えるようなものは面接官によっては悪印象ですから避けておきましょう。
また、ハイブランドのロゴが目立つようなアイテムも良いイメージを持たれない傾向がありますので、面接では身に付けないようにしましょう。
ブランドイメージから大きく外れている
ブランドイメージから大きく外れたコーディネートの場合、応募先のブランドや企業について勉強(リサーチ)不足であることが感じられ、意欲を疑われる可能性があります。
また、本人のこだわりがあってあえて外している場合も、「このブランドに長く勤めてくれるのか」に不安を持たれます。リサーチ不足や入社意欲に欠けると判断されるようなコーディネートは止めておきましょう。
アパレル系販売職の面接、アイテム別のポイント
アパレル系販売職の面接では、一般的な企業の面接ではNGとされるものでもブランド系統によってはOKである場合があります。アイテム別にポイントをご紹介します。
靴
アパレル系では、他業種の面接では絶対NGのスニーカーやブーツも許容される場合が多いでしょう。季節性も大事なので、だらしなく見えない、ファッション性のあるものであればサンダルやタイツもアリ。ただし、応募先ブランドの店舗に立つイメージが湧く範囲でまとめましょう。あえて攻めたファッションをする必要はないので、迷ったら無難な方を選びましょう。
バッグ
一般的な面接シーンと同じく、機能面では「A4サイズの書類が入ること」「口が閉じるもの」「足元に置いても自立するもの」がおすすめです。足元に置けないクラッチバッグやショルダーバッグ、自立しないリュックは避けた方が良いでしょう。それらを満たしていれば、デザインでのNGは特にありません。
サブバッグを持つこと自体はハッキリNGとは言えませんが、競合他社のショッパーバッグはもちろんNGですし、ジャンルが違いすぎるブランドのものも好印象にはつながらないでしょう。
アクセサリー
アクセサリーで絶対NGとされるアイテムはほとんどなく、バングルやピアス、派手めのデザインでもトータルコーディネートで良ければ問題ないブランドも多いようです。
ただし、ブランドによって許容範囲が大きく異なるというのが実際のところなので、ブランドイメージ内のアイテムとしましょう。面接ですから、迷うならシンプルな方、着けない方が正解です。
帽子
アパレル系の面接でも、帽子は基本的には避けた方が良いでしょう。帽子をしているなら、外して手に持って面接会場へ入りましょう。もちろん、帽子ブランドの面接で「着用指定」がある場合は別です。
カラコン・眼鏡
カラコンはナチュラルカラーなら許容のブランドも多いですが、それ以外のカラーや盛りすぎのものは面接では止めておきましょう。メイクもファッションの一部ですから、つけまつげやまつげエクステもナチュラルなものがおすすめです。
眼鏡は視力矯正目的のものはもちろん問題なく、伊達メガネもブランドイメージに合うものなら問題ありません。反対に、接客時に違和感があるほどの強い矯正眼鏡なら、コンタクトレンズの方がおすすめです。
香水・ネイル
アパレル系の面接でもキツイ香水の香りは悪印象です。控えめか、迷うようなら付けないで臨みましょう。
ネイルもブランド毎にルールが大きく異なる部分ですから、面接時にはなるべくナチュラルなカラーにして、清潔感の方を優先させましょう。
髪色・髪型も「清潔感」と「ブランドイメージ」がポイント
髪型も「清潔感」と「ブランドイメージに合う」ことが大前提です。その姿で応募先ブランドの店舗に立てるかどうかを基準に考えればOK。就活ではないので、茶髪NGということはありませんが、コンサバ系なら暗めにする、カジュアル系でもナチュラル寄りなら地毛に近い髪色にする、といったブランドイメージに沿った対策を取りましょう。
金髪はほとんどのブランドでNG、または好まれないと考えておいた方が良いようです。もちろんプリン状態は清潔感の観点から悪印象なので、染め直してから面接に臨みましょう。
「ぼさぼさではない」「(面接なので)顔が隠れていない」「お辞儀しても邪魔にならない」などの配慮を感じられるかどうかもみられています。面接の場に適したTPOをわきまえているという印象を持たれることが大事です。
ブランドによって正解はバラバラ!必ず自分で調べて判断を
アパレル系販売職の面接での服装についてポイントをご紹介しました。一般的な面接ファッションとOK/NGの線引きが異なるものが多いですが、ブランドによってその許容範囲は大きく異なる場合があります。面接の前に必ずご自身で求人情報や面接情報を調べて、その企業のルールに即したファッションで臨みましょう。
『女の転職アカデミア』とは
『女の転職type』がお届けする、
転職活動を一歩前に進めるためのお役立ちコーナーです。
転職を成功させて理想の未来を手に入れるには、自己分析から企業研究、書類作成に面接対策まで、やることがたくさん! その途中で、悩み立ち止まってしまうこともあるでしょう。そんな時、ここに来たらヒントが得られて道が開ける。皆さんにとって、そんな場所でありたいと願って運営しています。