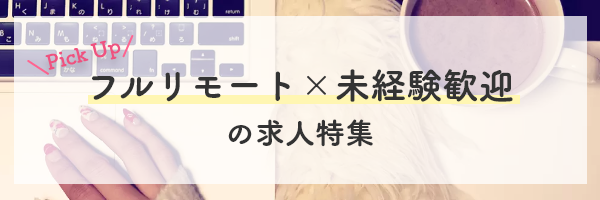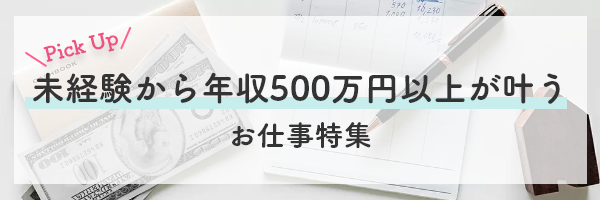面接後のお礼状は必要?書き方とポイントを紹介
面接を受けた企業に対して、お礼状は送付した方が良いのでしょうか?
日常的に書くものでもないので、いざお礼状を書きたいと思った際にマナーに自信がない人も多いはず。そこで、この記事では面接後にお礼状を送る必要性や送る際のポイント、お礼状の書き方や例文を紹介していきます。
面接後のお礼状は必要?
学生向けの就活マナー講習などでは、面接の際にはお礼状を送付する方が良いと教えられるケースもあります。しかし、中途採用の面接後のお礼状は本当に必要なのでしょうか。
面接のお礼状は必ず送る必要はない
面接をしてくれた企業や採用担当者に対してお礼状を送ることが、選考で有利になると考えている人もいるかもしれません。しかし、実は必ず送付しなければならないものではないというのが現代の一般的な考え方です。
理由は、転職活動中の企業とのやりとりはほとんどメールで行われますし、選考結果の通知も速い場合が多く、郵送のお礼状がそのスピード感に合わない可能性が高いからです。
また、お礼状を送付したからといって採否には影響を与えず、ましてやお礼状ひとつで採否が覆るものではありません。ただし、面接に対してお礼をするという行為によって、採用担当者に丁寧な印象を持たれる可能性が高くなるのは事実です。次のようなシーンではお礼状が効果的かもしれません。
採否が微妙なとき
上記でご紹介したように、基本的にはお礼状の送付が採用に影響するというものではありません。しかし、他の候補者と選考を僅差で競い合うなど、採否が微妙なときは有利になる可能性もあります。
お礼状は、面接の機会を与えてくれた企業に対する感謝の意を表すものですが、その機会に企業に対する意気込みをアピールするツールともなり得ます。ギリギリのラインで採否を迷っている際には、熱意や人柄が最後のひと押しになることもあります。やらなくても良いことだけれど感謝を伝えたいから、という謙虚さや心配りが好印象につながります。
同条件の候補者が多数いるとき
転職したい企業や職種によっては採用枠が少なく、応募者が殺到している場合があります。企業が多数の応募者を短い期間の間に面接して候補者を絞っているような場合には、お礼状を送付することで差別化を狙うことができます。
つまり、他の人は送らないものをあなたが送ることで採用担当者の目に留まるきっかけになる可能性があるということです。
丁寧なお礼状を送付することで、他の候補者よりも印象がよくなることもありますから、定型文ではない本気のメッセージを伝えるべきでしょう。
お礼状を送る際の7つの注意点

面接に対するお礼状を送付する際には、送付するタイミングや誤字脱字などに注意しなければなりません。ここでは、お礼状を送付する際に気を付けるべき7つの注意点について解説していきます。
1、お礼状はできるだけ面接当日に出す
面接が終わった後、どのタイミングでお礼状を送付すれば良いか悩む人も多いのではないでしょうか。お礼状を送付するタイミングは、できるだけ面接当日に送付するようにしましょう。
なぜなら、面接官に自分の印象が残っているうちに届いた方が、あなたの印象と内容が結びつきやすいからです。メールやはがき、封書といった手段に関わらず、できるだけ早めに送付することが大切です。
2、お礼状の宛先は採用担当宛
面接では採用担当者以外の人が面接をしてくれることも珍しくありません。その場合でもお礼状は採用担当者宛てに送付するのが一般的です。
お礼状の目的は面接に対する感謝の意を伝えることであるため、採用担当宛に送付して感謝をまとめて伝えても問題はありません。
面接で特に長くやり取りをした相手がいた場合には、その相手に宛てた文章を記載するとより丁寧です。
3、「御中」と「様」は正しく使い分ける
企業や部署宛に送付する場合は「御中」、採用担当者などの個人宛に送付する場合は「様」を使いましょう。
採用担当者とのやり取りが少なく、個人名がわからないケースも考えられます。このような場合は、「中途採用ご担当者様」宛に送付すると良いでしょう。部署名が分かる場合は部署名も忘れないように記入しましょう。
「◯◯会社御中 採用ご担当者様」といったように、「御中」と「様」を一緒に使う間違いがよく見られるので注意しましょう。
4、敬語表現を使用する
メールでも同様のことが言えますが、ビジネスマナーをきちんと守って正しい日本語を使うことはとても大切です。
以下では、お礼状によく用いられる敬語表現を表で示しているので参考にしてみてください。
| お礼状の相手先 | 正しい敬語表現 |
| 企業(株式会社、有限会社など) | 貴社 |
| 銀行 | 貴行 |
| 団体(NPO法人含む) | 貴団体、貴法人 |
| 各種事務所 | 貴事務所 |
| 市役所、区役所 | 貴役所 |
| 官公庁 | 貴庁、貴省 |
| 病院・医院・クリニック | 貴院 |
| 各種施設(福祉施設、介護施設ほか) | 貴施設 |
| 各種店舗(お店、ショップ) | 貴店 |
このようにお礼状の相手先によって敬語表現が異なるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
5、「横書き」よりも「縦書き」が礼儀正しい
パソコンやスマホで見るWeb上の文章は、ほとんどが横書きです。また、メールも横書きが一般的なので、はがきや封書の場合は縦書きと横書きのどちらで書けば良いか悩みがちです。
ビジネスマナーとしては目上の人に対してお礼状を送付する場合、横書きは失礼と考えられています。そのため、お礼状でははがきでも封書でも縦書きが鉄則です。
⑤面接候補日は5つ以上伝える
面接候補日を聞かれたら、最短で可能な日時から順に5つ以上伝えておきましょう。ピンポイントで相手の都合が合う可能性は低いので、可能な限りこちらの都合の良い日時で押さえるためです。
6、定型文よりもオリジナル文の手書き
面接に対するお礼状を送付する場合は、手書きをおすすめします。
なぜならあらかじめ印字されたものよりも、手書きの方がお礼状としての効果を最大限に発揮してくれるからです。達筆でなくても一生懸命丁寧に書かれた手紙は、面接に対するお礼の気持ちや入社を望む強い気持ちが伝わりやすくなります。
ただし、業種や企業の考え方によっては読みにくい手書きよりも、パソコンソフトで作成したお礼状の方が読みやすさ、効率性の観点から良しとする場合もあります。面接官や担当者のタイプを見極めて手書きにすべきかどうかは判断したいところです。
7.誤字脱字に注意
印象を悪くしないためには、当然のことながら誤字脱字には細心の注意を払いましょう。なぜなら誤字脱字があるお礼状を受け取った場合、文章の質を下げることに加えて自分の信用を失いかねないからです。
万が一間違えた場合は、必ず新しいはがきや便箋を使って書き直すようにしましょう。少しのミスであっても、決して修正テープは使わないことが鉄則です。
特に企業名や採用担当者の名前など、絶対に間違えてはいけない部分については何度もチェックするようにしましょう。
面接のお礼状で書くべき3つの要素

お礼状の送付は採用担当者からの印象アップが狙えるだけでなく、採否が微妙なときに有利に働く可能性が期待できます。しかし、単にお礼状を送付すれば良いという訳ではなく、以下のような要素が盛り込まれていることが大切です。
1、面接の時間を作ってくれたことへのお礼
お礼状にはまず企業や採用担当者に対して面接の機会を与えてくれた感謝の意を述べるようにしましょう。「お礼」を伝えることが最も大きな目的なので、時候の挨拶や名前の直後に述べるのが基本です。感謝の気持ちを長々と述べたいかもしれませんが、相手にスムーズに伝わるように簡潔な文章を心掛けましょう。
2、面接の感想や興味をもったこと
冒頭で感謝の意を述べた後は、面接の際に抱いた感想や興味をもったことを伝えるようにしましょう。例えば、面接官から聞いた企業説明の中で最も印象に残ったこと、感動したことを簡潔に述べます。
抽象的な内容よりも、どの部分に対してどのように感じたのかといった具体的な内容を挙げるとより伝わりやすくなります。ただの形式的な内容にならないように注意しましょう。
3、面接後に感じた志望への強い気持ちを加える
面接に対する感想などを述べた後は、面接後に感じた志望への強い気持ちを伝えましょう。例えば、面接官とのやりとりから入社後に尽力したい仕事内容が明確になった、深く知ってより志望度が高まったことなどを文章に表します。
ただし、ここで自己PRのような文章をつけてしまうのはNGです。
なぜなら面接で上手く伝えることができなかったからお礼状で補足している、といったマイナスな印象につながってしまう可能性があるからです。どんなに入社を強く望んでいても、長くだらだらとした文章にならないように注意しましょう。
面接のお礼状の例文
お礼状で書くべきポイントを押さえたところで、次に具体的な書き方を確認しておきましょう。ここでは、例文を交えながらお礼状の書き方をご紹介していきます。
お礼状の例文
一般的なお礼状の例文は、以下の通りです。
まずは採用担当者の役職や名前、続けて頭語と時候の挨拶を書きます。
●株式会社○○
採用ご担当 ○○様
●拝啓
●〇〇の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
次に、面接の機会を与えてもらったことへのお礼を述べていきます。
●【面接で時間を作ってくれたことへのお礼】
(例文)先日はお忙しいところ、面接の機会をいただき、誠にありがとうございました。
面接では、○○のご説明をいただき、大変感謝しております。
「面接のお礼状で書くべき3つのポイント」でもご紹介したように、面接の感想や興味を持ったこと、面接後に感じた志望への強い気持ちを簡潔に述べます。
●【面接の感想や興味をもったこと】
(例文)○○についての現場のお話は私にとって意義深く大変勉強になりました。
特に○○という点に非常に共感いたしまして、益々貴社で働かせていただきたいという気持ちが強くなりました。
●【面接後に感じた志望への強い気持ち】
(例文)仕事に対する意欲が増し、前職の経験を活かしてぜひとも貴社に貢献したいと考えております。
今後共、なにとぞ宜しくお願いいたします。
最後に結びの挨拶を述べ、末語と日付、名前を記して締めくくります。
●末筆ながら、貴社の益々のご発展を心から祈願いたします。
●敬具
●○○○○年○○月○○日
●名前
お礼状で書くべき3つのポイントの中でも、特に「面接の感想や興味を持ったこと」についてはなるべく具体的にすると良いでしょう。面接官とのやり取りで、どの部分に興味をもったのか、感動したのかといったことも具体化させましょう。
【はがき・封筒・メール】それぞれの送り方

面接のお礼状を送付する方法は、主にはがき、封筒、メールの3種類が利用されています。メールは、面接後に最もスピーディーにお礼を伝えられる方法です。
近年の採用では、インターネット経由での応募も増えています。面接の日時や採否の連絡もメールで行う企業も多くなったので、お礼状はどのような方法で送付すれば良いか悩みがちです。上記でも触れたように、業種や社風によっても反応は分かれるところですから、それぞれの印象の違いなどを押さえておきましょう。
メールでのお礼状
これまでの勤務先やプライベートでも、手紙よりもメールのほうが使い慣れているという人も多いのではないでしょうか。
メールできちんとお礼状が送ることは、ビジネスマナーを身に付けていることやパソコンスキルの判断材料を企業に伝えることになります。また、最も早く相手に届くので、面接官に自分の印象が残っている状態で、良い印象を付け加えることができるでしょう。
ただし、メールは気軽に連絡できるという利点がある一方で、手紙に比べるとていねいな印象が弱くなるので注意が必要です。外資企業、IT系企業、ベンチャー企業など、スピード感を重要視する企業の場合、メールでのお礼状は向いています。
便箋・封筒でのお礼状
封書はていねいな印象を最も強く伝えられる方法です。ホスピタリティ精神が求められる職種やきめ細やかな対応が求められる職場への転職を希望する場合には、封書を使ったていねいなお礼状が印象アップに繋がります。
特に、金融系やメーカー系などの老舗企業や、礼儀を重んじる社風の企業にも向いています。
ただし、メールと異なり自筆で書く必要があるため、くせ字には気をつけましょう。また、ボールペンを使いがちですが、黒または紺の万年筆かインクペンを使用するようにしましょう。便箋は縦書きで、ビジネスシーンに適した白や無地のものを選ぶことが大切です。
はがきでのお礼状
インターネットが普及した現代、はがきや封書の使用量は年々減少しています。しかし、ビジネスシーンでは取引先や顧客に対して、はがきでのお礼状が多く使われています。
はがきは封書と比べて簡素な印象を与えやすいものの、お礼状としては十分な効果を発揮してくれます。
相手の面接官がどんな人だったかを把握して、効果がありそうな人であればぜひ活用してみるのも良いでしょう。
面接後のお礼状はビジネスマナーを守って
面接に対するお礼状は全ての企業に送る必要はありませんが、絶対に後悔したくないのであれば想いを文章にして伝えることはとても大切なことです。お礼状を出したことにより、後から「その心遣いが採用の決め手になった」と言われるケースもゼロではありません。
ただし、単にお礼状を送付すれば良いという訳ではなく、感謝の意が伝わらなければ意味がありません。誤字脱字や書き方のマナー違反を始め、あからさまに媚を売るような文書はかえって悪い印象につながってしまう恐れもあります。
採否のためにお礼状を書くのではなく、お礼を伝える気持ちや習慣があなた自身の評価に繋がるということを心にとどめ、転職活動の参考にしてくださいね。
『女の転職アカデミア』とは
『女の転職type』がお届けする、
転職活動を一歩前に進めるためのお役立ちコーナーです。
転職を成功させて理想の未来を手に入れるには、自己分析から企業研究、書類作成に面接対策まで、やることがたくさん! その途中で、悩み立ち止まってしまうこともあるでしょう。そんな時、ここに来たらヒントが得られて道が開ける。皆さんにとって、そんな場所でありたいと願って運営しています。