職場の人間関係でギスギス。ストレスに押しつぶされそうになった時の頭の切り替え方【精神科医・藤野智哉】

精神科医・藤野智哉さんが現代社会を生きる働く女性が身に付けておきたい「心の防衛術」について解説する本連載。
今回は、「職場の人間関係疲れ」に悩む読者からの相談に、答えてくれました。

藤野智哉さん
精神科医。産業医。秋田大学医学部卒業。幼少期に川崎病に罹患。心臓に冠動脈瘤という障害が残り、現在も治療を続けている。障害とともに生きることで学んできた考え方と、精神科医としての知見を発信している。精神鑑定などの司法精神医学分野にも興味を持ち、医療刑務所の医師や看護学校の非常勤講師なども務める
Twitter:@tomoyafujino
職場のチームに全く考え方の合わない人がいて、いつも意見がぶつかってしまい、仕事がうまく進まないことにイライラします。
どちらかの考え方が間違っているというのではなく、とにかく考え方が合わないので折り合いがつかないのです。
職場でもギスギスしてしまうし、仕事の進捗には支障が出るし、家に帰ってからもその相手のことを思い出してはイライラして苦しくなってしまいます、どうすればいいでしょうか。
回答:「これってもったいなくない?」自分に問い掛けて
職場の人間関係って、すごく難しいですよね。これが趣味のサークルなどであれば、「距離を取るのが一番です」とアドバイスするんですが、職場となると、そう簡単に「その人と距離を置いて」とはいかないものです。
しかも最近ではテレワークが普及し、自宅=オフィスというケースも増えています。すると、物理的にも、心理的にも仕事のことばかり考えやすくなり、ストレスを溜め込んでしまいがちです。
その上でアドバイスするとしたら、「この人のことを考えてイライラしている時間、もったいなくない?」と考え方を切り替えてみること。
人間、事故にあえば明日にでも死ぬかもしれません。なのに、「あぁ、嫌いな奴のことばっかり考えてたな」って思いながら最後の時を迎えるなんて誰でも嫌じゃないですか。
「あの人の顔を思い浮かべながら死ぬなんてごめんだ!」と思ったら、もっと楽しいことを考えようと頭を切り替えられるかもしれません。

そして、前提なのですが、職場の人と仲良くすることって、決してマストじゃないですよね。「仲良くしなければいけないのに……」と思っているんだとしたら、その考え方を見直してみるという手もあります。
協調性を大事にする日本人は、「仲良きことは良きこと」というのが前提になってしまいがちなのですが、仕事仲間はあくまで仕事仲間。「目的が達成できれば、それでいいじゃん」と割り切ることもできますよね。
そして、仕事には得たい利益や達成したい目標が必ずありますから、いくら意見が合わない人がチームにいても、目的達成のための合理的な方法を双方で考えてみて、どちらがより合理的かを比べてみて、どちらの方法論を採用するか上司に判断をくだしてもらえれば、答えが明確に出ることも多いはず。
一見すると意見はぶつかっているけれど、目指している目的は一緒だった、なんてことはよくあると思いますよ。
「いつもぶつかる」それってホント? 事実と感情を区別して考えて
ただ、Cさんには耳の痛い話かもしれませんが、一度冷静に確認した方がいいのは、自分が苦手だと思っている相手が、Cさん以外の人ともうまくやれていないのかどうかです。
他の人とは人間関係もよく、職場でも評価されており、なおかつ特に誰ともぶつかっている様子がない。なのに、なぜか自分とだけは意見が合わない。
そういう状況なのであれば、Cさん自身にも問題があるのではないでしょうか。
相談文を見ると、「全く意見が合わない」「いつも意見がぶつかる」とあります。「全く」「いつも」などの極端な言葉が使われていますが、事実は本当にそうなのでしょうか?
人間は成長するにつれ、物事にはいろいろな面があり、必ずしも0か100かではないことを学びます。

例えば、『ドラえもん』のジャイアンは、乱暴者だしのび太のことをいじめるし、ちょっと困った子です。でも、人情にあついところがあり、頼れる場面もある。「悪いところもあるけど、彼にはいいところもあるよね」って大体の大人は思うわけです。
ところが、ストレスで思考が硬直化すると、相手のことを0か100かでしか捉えられなくなってしまう。ジャイアンは完全に悪人だ! と思い込むわけです。
すると、「何て嫌な奴なんだ」「何をしても腹が立つ」というように、さらにストレスがたまる悪循環に陥ってしまうのです。
Cさんも実は、同じ状況にいませんか? 感情的になってしまう部分を一度落ち着けて、「事実」をありのまま受け止めてみれば、10回に1回くらいは意見が合うこともあるのでは? だって、同じ目的に向かう組織の中で働いているわけですから。
100%相性が良くない! と決めつけるのではなく、「まぁ、相性の良さは20%くらいかな」くらいに受け止められるようになった方が、自分自身の力みがとれます。
そして、「嫌いだ」「苦手だ」と思い込んでいる人に対してのCさんの態度は、きっとそのお相手にも伝わっていると思います。すると、相手はもっと心を閉ざすし、緊張してしまうし、あなたへの態度も余計に悪くなる。イライラして相手に接しても、結局自分にとってもいい結果は生まれません。
感情を客観視して、自分をコントロールする
また、「自分の感情」と「事実」を区別して考えるためには、感情を客観視できるようにすることが有効です。自分の感情を客観視する方法としては、具体的に以下のようなものがあります。
●「感情の壺」を描いてみる
壺の絵を描き、どのような感情がどのくらいまで入っているかを描きだしてみましょう。
今、壺から「『怒り』があふれそう」「『悲しみ』が増えてきている」のように、ビジュアル化して、自分が今どういう感情に支配されているのかを理解するようにします。
●感情を擬人化してみる
あるいは、「カナシミちゃん」「イライラちゃん」のように感情を擬人化し、「イライラちゃんが暴れ出した」のように捉えてみる。すると、自分の感情から一歩引いた視点が生まれて、「悲しみ」や「怒り」などの感情から一定の距離を置くことができます。
職場でもしも怒りがこみ上げたら、「お! またイライラちゃんが来たか~! 少し経ったら帰ってね~」って頭の中で唱えてみてください。いつもより冷静でいられると思いますよ。

今回紹介した方法も一例ではありますが、自分に合ったセルフコントロールの方法を知っておくと、いざというときも安心です。
仕事をしていれば、ストレスを感じたり、傷ついたり、不安を感じたり、感情的に疲れることがあるのは避けられません。そんな中でも健やかな毎日を送っていくために、自分なりの防衛術を身に付けておきましょう。
書籍紹介
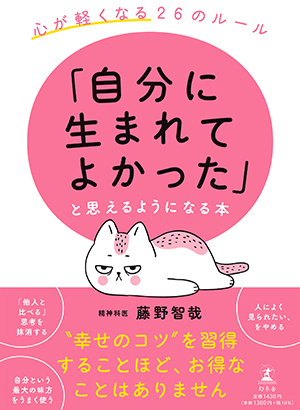
『「自分に生まれてよかった」と思えるようになる本 心が軽くなる26のルール』(藤野智哉著:幻冬舎)
SNS時代、人と比べて自分に自信を無くしてしまう人は多くいる。でも、一度きりの人生なのに、そうやって他人と自分を比べて落ち込むばかりの毎日でいいの……? 「自分に生まれてよかった」と心から思えるようになるための、切り替え術を精神科医・藤野智哉さんが解説します
取材・文/夏野かおる





