転職後の緊張疲れに要注意? 精神科医が教える「頑張りすぎる人」のための休息の基本【医師監修】
長く働き続けるためには、頑張るだけじゃなく、心とカラダをしっかり休める時間を持つことも大切。この特集では、ヘルシーなワークライフをつくる“いい休み方”を新提案。明日の元気な自分をつくる「休み方改革」を始めよう!
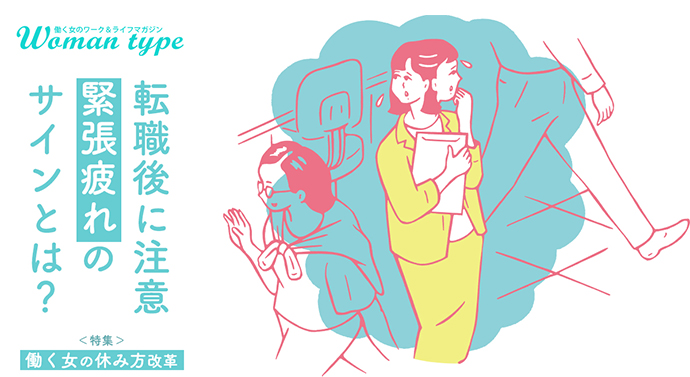
4月に部署異動や転職などで、新しい環境に飛び込んだ人は多いはず。
期待を持って新天地へ飛び込んだとしても、慣れない環境・仕事・人間関係などさまざまな変化が一気に押し寄せて、5月に入ってからどっと疲れを感じている人や、緊張疲れから心身の不調を感じ始めた人もいるのでは?
そんな新しい環境でついつい頑張りすぎてしまう女性たちのために、フェミナス産業医・労働衛生コンサルタント事務所の代表統括産業医・精神科医である石井りな先生が、緊張を和らげる働き方のコツや、新しい環境に飛び込んだばかりの人にこそ実践してほしい「いい休み方」のポイントについて解説してくれた。
転職後に疲れて体調を崩しやすい「0・100思考」の落とし穴

──そもそも、転職で新しい環境に飛び込んだときに、ストレスや疲労を感じやすくなるのは一体なぜなのでしょうか?
環境の変化は人間にとってストレッサー(ストレスを与える刺激)になります。
知らない人に囲まれて、自分の知らないルールの上で仕事をするというのは、誰にとっても不安なものだし、緊張を強いられるもの。
何をしたらどうなるのか結果の予測がつきづらく、考えることや気にしなければいけないことがたくさんあるので、知らず知らずのうちに疲れやすくなります。
ーー新しい環境にすぐ適応できる人もいますが、環境になじめず体調を崩しやすい人に何か特長はありますか?
大きく分けて二つあって、一つは期待と現実のギャップが大きい人ですね。
入社前は「きっとすてきな会社に違いない」「自分はここで活躍できるはず」という期待を膨らませていたのに、現実は「そうじゃなかった」と感じている人は余計にストレスを抱えがちです。
特に、未経験の業界に転職したり、未経験の仕事にチャレンジした人などは、「思っていた仕事と違った」と言って面談にいらっしゃる方も多くいます。
ギャップに悩みながらも、周囲の期待に応えようと頑張りすぎてしまい、結果的にメンタルに不調をきたしてしまうケースがよく見られますね。
もう一つは、物ごとを0か100かでとらえる、いわゆる「白黒思考」の人。
「転職直後なんだから全力で頑張るべき」「周りの期待には必ず応えるべき」という考えに固執して自分を追い込みすぎてしまったり、前職と比較して現職の人たちのやり方を否定的にとらえてしまったり。
新しい環境における仕事の進め方や人間関係について、「そういうやり方もあるのか」「こういう人もいるのか」というふうに柔軟に考えられない人は、ストレスを強く感じて体調を崩してしまいがちです。
もし自分がそういう思考に陥ってしまっているかも……と感じたら、いったん「~~べき」や「絶対~~」という言葉をなるべく使わないようにしてみることをおすすめします。
まっさらな気持ちで、新しい環境での仕事をまずは受け入れる心を持ってみる。「こういう考え方もあり」「こういうやり方もあり」と考えられるようになるだけで、心が疲れにくくなると思いますよ。
動悸・冷や汗・手の震え…緊張疲れのサイン

──新しい環境に飛び込んだばかりのときは、気持ちが張りつめていたり、頑張りすぎていたりするので、自分の疲れに気づきにくいこともあると思います。どんなサインが体にあらわれたら注意した方がいいですか?
人は緊張状態にあると、交感神経が高まりすぎてしまうことがあります。
すると、動悸や冷や汗、声や手が震える、挙動不審になる……などの症状があらわれやすくなりますね。それによって仕事や日常生活に支障をきたすようなら要注意です。
また、緊張状態にあると、自分の異変に自分で気付けないことも。そういうときは、意外と周りの人の方が敏感に変化に気付いてくれるかもしれません。
人と話したときに「最近ちょっと調子悪い?」「大丈夫?」などと声をかけてもらったときは、自分が思っている以上に異変が出ている可能性があるので、少し冷静になって以前の自分と今の自分を比較してみるといいですね。
ーー「ちょっと気になる」程度の異変でも、病院には行った方がいいのでしょうか?
もちろん、いつもと違う気になる症状が出ているなら病院に行ってみるといいと思いますよ。それによって、病気が深刻なものにならなくて済んだり、対処法を見つけられたりする可能性があります。
ただ、転職して1カ月くらいの期間だと、環境に慣れていないのも、仕事についていけないのも当たり前だったりはするので、心身の不調でていないのであれば、3カ月くらいは様子を見てもいいかもしれません。
以前、入社から1カ月程度のところで産業医面談にやってきて、緊張やプレッシャーから「仕事がうまくいかない」と悩みを打ち明けてくれた方がいました。
ただ、入社3カ月がたったころにもう一度お話をしてみると、ずいぶん社内の環境にも慣れて「もう落ち着いて仕事ができるようになった」とおっしゃっていた方もいました。
「この会社は合わない」「ここで仕事を続けてもうまくいかない」というような判断は、あまり早くしすぎない方がいいかなとは思いますね。
規則正しい食・睡眠・運動習慣が「いい休息」につながる

──柔軟な考え方をするようにするなど、なるべく疲れない働き方を意識するのとともに、緊張して疲れがたまったと感じるときに実践するといい休み方は?
まず、基本は食事をしっかりとること、十分な睡眠をとること、適度に運動すること、この三つを意識することが大切です。
睡眠時間に関しては、人によって必要な時間は多少違いますが、目安として7~8時間は日々の睡眠時間を確保できるといいと思います。
また、夜にカラオケに行くとか、休日にスポーツをするとか、定期的にリフレッシュすることも大事なんですけど、それは元気な体があってこそできること。
体がへとへとなのに気持ちのリフレッシュだけしても、休んだことにはなっていません。
なので、当たり前のように聞こえるかもしれませんが、まずは「食事・睡眠・運動」この三つが元気を回復する上では大切です。
そして、心を元気にすることは、人によってさまざまです。自分が「楽しい」「ワクワクする」と思うことに取り組んでみてください。
おすすめなのは、普段から「これが楽しい」「これをすることが好き」というもののリストをつくっておくこと。
今後も異動や転職で新しい職場に移ることがあるかもしれないし、そうじゃなくても、女性は特にライフステージによってさまざまな変化を経験します。
その都度、「新しい環境」にうまく適応して、元気に仕事を続けていくために、20代のうちから自分をケアする方法を習得しておけると安心ですね。

フェミナス産業医・労働衛生コンサルタント事務所
代表統括産業医・精神科医
石井りなさん
独立行政法人東京医療センター(目黒区)にて内科・外科・救命救急を中心に初期研修後、同病院精神科にて研さんを積む。その後、医療法人高仁会戸田病院、川口クリニック、大石記念病院等で、軽症から重症までの精神疾患診療に従事しながらリワーク外来などを担当。並行して、精神分析・力動的精神療法、認知行動療法の精神療法を学び日々の診療に取り入れている。 2010年より産業医として活動し、フェミナス産業医事務所を設立。医療と職場双方の視点から多数の難しいケースを復職・就労定着へと導く。 16年、働く人のヘルスケアを行う「九段下駅前ココクリニック」に参画。 順天堂大学大学院衛生学にて、衛生学全般の他、主治医と産業医の連携、仕事と疾病治療の両立支援を研究。 作業環境の評価や産業保健法務についても学ぶ。現在は、企業から頼りにされるプロフェッショナル産業医の育成、産業医間の互助連携などに取り組む。自らの管理職経験も、産業医活動へ活かしている
>>フェミナス産業医事務所
取材・文/まゆ イラスト/石山好宏







