【Q&A】空気が読めない、遅刻を繰り返す…発達障害グレーゾーン部下の困った行動への対処法/公認心理師・舟木彩乃さん

いくら指摘しても同じミスを繰り返す、空気が読めない、なくしものや忘れ物が多く、遅刻してばかりーー。
医師から発達障害を診断されたわけではないけれど、発達障害の傾向がある……そんな「発達障害グレーゾーン」な部下に悩まされる上司が増えている。
懇切丁寧に仕事を教えても、部下の行動が全く変わらないばかりか、逆恨みされたり負の感情をぶつけられたり。お手上げ状態の上司も多いかもしれない。
そこで、公認心理師で『発達障害グレーゾーンの部下たち』(SBクリエイティブ)著者の舟木彩乃さんに、女性管理職からよく寄せられる相談三つとそれぞれのケースへの対処法を伝授してもらった。

ストレスマネジメント専門家、公認心理師
舟木彩乃さん
一般企業の人事部で働きながらカウンセラーに転身、その後、病院(精神科・心療内科)などの勤務と並行して筑波大学大学院に入学し、2020年に博士課程を修了。著書に『「首尾一貫感覚」で心を強くする』(小学館)、『過酷な環境でもなお「強い心」を保てた人たちに学ぶ「首尾一貫感覚」で逆境に強い自分をつくる方法』(河出書房新社)、近著に『「なんとかなる」と思えるレッスン』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『発達障害グレーゾーンの部下たち』(SBクリエイティブ)などがある(X:@funakiayano)
相談1:会議のときに「場の空気」を読んでくれない
部下の一人が、会議中に自分だけ話し続けたり、人の話を最後まで聞かずにさえぎったりしてしまいます。
ほかの人の発言を否定したり脈絡のない話をしたりするので議論がまとまらず、場の空気が悪くなるので困っているのですが……。
せっかく発言してくれているのに、こちらが話をさえぎったら傷つけてしまうのではないかと心配です。
回答:個別に話し合いの場を設けて、会議のルールを共有しよう

この相談内容のケースだと、会議中など「その場で注意しないと」と思ってしまう人も多いかもしれません。
ですが、みんなの前で注意したり否定したりするのは逆効果。発達障害グレーゾーンの方の中には繊細な方も多いため、人間関係に亀裂が入る可能性があります。
この場合に有効なのは、会議の後で対象の部下に声を掛けて、個別に相談の機会を持つことです。
発達障害グレーゾーンの部下自身は、悪気がない可能性が高いので、どういう発言をすると相手が傷つくのか、どうすれば会議の場がより良くなるのか、その場で丁寧に説明してみましょう。
また、会議をより良い場にするために分かりやすいルールを設けることも有効です。
例えば、「一人あたり発言は3分まで」「ほかの人の発言を否定しない」「誰かが発言しているときは、最後まで聞く」など、参加者に大切にしてほしいことを明文化して共有しておきます。
そして、特定の部下にだけこのルールを守らせようとするのではなく、「全員でやる」ことを意識してみてください。
部下に「自分だけ厳しくされている」などととらえられないように、伝え方や取り組み方に気を付ける必要があります。
相談2.なくしものが多く、いつも何かを探している
部下のデスクがいつもぐちゃぐちゃで、すぐになくしものをします。
PC上のデータ整理も苦手なようで、資料をどのフォルダにいれたのか分からなくなり、頻繁に探し物をしているような状態です。
時間のむだなので、整理整頓をちゃんとさせたいのですがどうすればいいのでしょうか……。
回答:サポート役と一緒に「しまう場所」を確認してもらいましょう

なくしものが多い人に業務上のトラブルを起こさないようにしてもらうためには、誰かがサポート役となって一緒に整理整頓をしてあげることが有効です。
大人なのに「ここまでやってあげなければいけないの……?」と言いたくなってしまう気持ちも分かります。ただ、身近なところにサポートしてくれる人がいるかどうかで、結果は大きく変わるものです。
例えば、サポート役の人から適宜、「この資料はどこにしまった?」「明日使う〇〇はどこにある?」と声掛けをしてみましょう。
その都度、探し物が見つからないことがあれば、何をどこにしまっておくべきなのか、所属する部門やチームの中で決めてあるルールを確認します。
そして、「大切な書類とはどういうものか」「個人の判断で勝手に捨ててはいけないものは何なのか」など、その定義も共有しながら片づける場所を確認していきましょう。
ただ、整理整頓が苦手なこと自体はもともとの特性なので、どんなに注意しても、ついうっかりなくしものをしてしまうことがあるかもしれません。
サポートを始めたばかりのころは「うっかり」の頻度も多く、確認する側がうんざりしてしまうことも多少はあるでしょう。
ただ、最初のうちは毎日確認する必要があったものが、1週間に1回になり、1カ月に1回になり……時間を重ねていくうちに、手離れしていくと思います。
最初のうちは辛抱強さが求められるかもしれませんが、結果的にチームのミスやトラブルが減り、その後の仕事が楽になっていくはずです。
相談3:何度も注意しているのに遅刻してくる
何度注意しても、部下の遅刻癖が抜けません。
「もっと早く家を出ようね」と伝えると、毎回反省したそぶりは見せるのですが、結局ほとんど毎日遅刻してきます。
どうすれば、遅刻をやめさせることができますか?
回答:家を出る前の行動を一緒に確認してみましょう

遅刻が多い人の場合、スケジュールを立てることが苦手な場合が多いようです。
すると、「早く家を出ないと」という意識はあっても、家を出る前にやるべきことが終わらず、家を出るのが遅くなってしまいます。
ですから、家を何時に出るには、何時までに何をしておく必要があるのか……朝のタイムスケジュール、TO DOリストを一緒に作ってあげることが有効です。
また、口では「反省している」と言いつつ遅刻が改善されない場合、客観的なデータを示した上で職場のルールに違反していることを伝えて問題点に気づいてもらいましょう。
例えば、上司側から「遅刻が多すぎるぞ」と言われても、「多い」の基準は部下によって異なる場合があります。
ですが、勤務表などのデータを一緒に見ながら「月の3分の2以上は遅刻しているね」「朝9時までに勤務を開始するのが職場のルールだよね」と問題点を指摘すれば、認識のずれはおきづらくなるはずです。
その上で、どうすればこの問題を一緒に解決していけるかを問い掛けてみましょう。
この時に大事なのは、悪いことばかりあげつらって責め立てないこと。その部下の良いところもたくさん褒めてあげてください。
そして、課題解決のために「一緒にやる」という姿勢を見せること。上司は自分の味方であると感じてもらうことも、行動改善を促す上では大事です。
完璧は目指さず、適度にスルーすることも大切

今回は、女性管理職の方からよくいただく三つの相談内容について、有効な対処法を紹介させていただきました。できそうなことからぜひ試してみていただければと思います。
ただ、うまくいかなかったからといって落ち込む必要はありません。発達障害の人や、発達障害グレーゾーンの人のマネジメントはとても難しいものなのです。
時には、徒労感を抱いたり、相手から負の感情をぶつけられてしまったりしてつらくなることもあると思います。そんな時には、自分自身を守ることが先決です。
絶対に起きてはいけないミスを防ぐ、業務上のトラブルを回避するためにやれることはやって、目を瞑れるところは「まあ、いいか」くらいの気持ちでスルーしてしまいましょう。
相手に完璧を求めないこと、自分自身も完璧を目指さないこと。この二つはとても大事です。
そして、職場でイライラしたり気持ちが落ち込んだりすることがあったら、切り替えを意識してみましょう。負の感情をずっと持ち続けないように、自分でオンオフのスイッチを切り替えてみてください。

例えば、自分が身を置く環境を変えてみることをおすすめします。職場にいるときに部下に対してイライラしてしまった場合、トイレに行ったり少し外を散歩したり、場所を変えて深呼吸してみましょう。気持ちが落ち着くと思います。
この気持ちの切り替えは、人によって何がスイッチになるかは異なるので、自分なりのスイッチを探すことがポイントです。
それが「お風呂に入ること」の人もいれば、「読書すること」だという人もいるでしょう。過去の自分の経験を思い起こして、やってみたら気分が良くなったことを探してみましょう。
何でも完璧にやり切ろうとせず、周囲の人の助けも借りながら、自分をケアすることも大事にしてくださいね。
【書籍紹介】
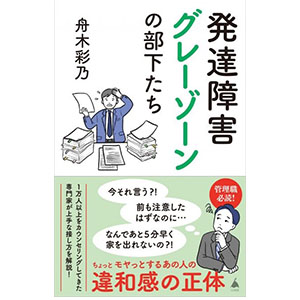
『発達障害グレーゾーンの部下たち』(著者:舟木彩乃)
>>書籍詳細
取材・文/栗原千明(編集部)








