減給、降格、サポート業務……それってなんだかヒドくない!? 最強ワーキングマザーに聞いた「育休後ジレンマ」の解消法
結婚、出産を経ても仕事に戻ってバリバリ働きたい。そのために今キャリアを築こうと頑張っている女性は多い。
でも、身近にいる先輩を見ていると、「時短だから減給」「サポート部署に異動」「マネジメント職から降格」――そんな復帰の仕方が当たり前みたい。
「あんなに仕事ができた先輩が、どうしてあんな対応されちゃうの!?」と、不当な対応をされているように見えてしまうワーキングマザー。
もし、自分がそんな立場になったらどうすればいいのだろうか。子どもを育てながら、当時の組織で最年少にして女性唯一のカンパニー・オフィサー(事業部長)にまで登りつめた、元「リクルート最強の母」、堂薗稚子さんにお話を伺った。
育休復帰後のまさかの格下げ! すべては「自分のせい」だった

株式会社ACT3 代表取締役 堂薗稚子さん
1969年生まれ。1992年上智大学文学部卒業後、リクルート入社。営業として数々の表彰を受ける。「リクルートブック」「就職ジャーナル」副編集長などを経験。2004年に第1子出産を経て翌年復職。07年に当時組織で最年少、女性唯一のカンパニーオフィサーに任用される。その後、第2子出産後はダイバーシティ推進マネジャーとして、ワーキングマザーで構成された営業組織を立ち上げ、女性の活躍を現場で強く推進。経営とともに真の女性活躍を推進したいという思いを強くし、13年に退職し、株式会社ACT3設立。現在は、女性活躍をテーマに、講演や執筆、企業向けにコンサルティングなどを行う
http://www.act-3.co.jp
実は、私自身、1人目の育休復帰の時に、3つの組織をまとめるマネジャーからいちチームのリーダー職に下がった経験があるんです。
リクルートの制度上、形の上では昇格・降格の概念がないのですが、実際の“格下げ感”はハンパなかったですよ。
育休中は「みんな、私がいなくて困ってるんだろうなあ」なんて、傲慢なことを考えていましたから、それこそ“不当だ”と信じて疑わなかった。
さらに傲慢なことに、「私以上にマネージャーに適任な人なんていない」と、資料まで作って、担当役員のところに乗り込みました(笑)。
でも、あっさり言われたんです。「そんなんだから、おまえはダメなんだ」って。「おまえの弱点は外部環境によってパフォーマンスが変わること。そのスタンスが変わらないうちは、俺はおまえを動かす気はないから」とまで言われました。
大ショックですよ。一番衝撃を受けたのは、「あれ、全部私のせいなの?」ってことでした。
ただ、「言われてみればそうかも……」と思えるフシもあったんです。でもどうしても悔しくて、「見てろよ、絶対後悔させてやる!」とも思いましたけど(笑)。
だから、そこからは働きましたね。わき目もふらず。そうしたら、自分が格下げになった理由が1年もしないうちに分かってきたんです。というか、夢中で働いていたら、いつの間にか評価なんか気にならなくなっていて、そこで気付いたんです。
「育休上がりだからってヒドイ」とか、「人事、何やってんのよ」みたいなことを思っているうちは、不純物が混じっている
というか、要するに甘えてるだけだったんですよ。
育休復帰後、2年でカンパニー・オフィサー(事業部長)に昇進したときに、例の役員にこう言われたんです。「おまえをこのポジションに就かせるには、あのままではダメだと思った」って。
本当にそうだったんだろうなって、その時にやっと、会社の采配に感謝できましたね。
キーマンは「直の上司」
密なコミュニケーションで自分好みに育成する
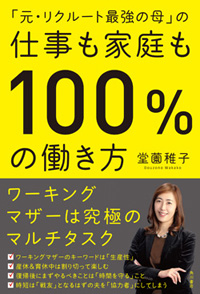
『「元・リクルート最強の母」の仕事も家庭も100%の働き方』(著者:堂薗 稚子/1,404 円/KADOKAWA/角川書店)
「仕事も子育ても両立したい! 」と思っても現実はなかなか難しいもの。それにも負けず、子どもを育てながらてカンパニーオフィサーになった著者の働き方を紹介
そんな経験をしてきた私が、これからワーキングマザーになる皆さんにアドバイスをするとしたら、まず、「上司を味方につけなさい」ということです。
育休から復帰した女性部下を何人も見てきましたが、彼女たちは「慣らし復帰期→泣きゴト期→自走期」というプロセスを通るんです。
もう笑っちゃうくらい、全員が間違いなく通る。で、大切なのは、最初の「慣らし復帰期」。
これは、夫との家事分担のバランスを見たり、保育園に預けた子どもがどのくらいの頻度で熱を出すのかを知ったり、要するに「仕事と家庭の両立スタイルをどう整えていくのか」という試行錯誤の時期です。
特に第1子の育休復帰だと、母親本人も初めてのことだらけだから、保育園から電話が来たといって焦り、夫が協力してくれないといって怒り、同僚に気を遣い過ぎて疲れ……と、環境に振り回されまくります。
ところが、子どものいる女性部下を持った経験が少ない上に、妻が専業主婦だったりして両立の大変さがピンときていない上司は、この最初の数カ月だけ見て評価したりするんです。
「こんなに休むなんて思わなかったよ」とか、「いつも時間を気にして仕事に身が入ってない」とか言って。ムカつくでしょ。でも、こういう不本意な事態を避けるには、自分から上司に自己開示していくしかないんです。
妊娠はプライベートなことでもあるし、特に男性の上司とはコミュニケーションを避ける女性が多いんです。「どうせ、言ったって分からない」とかね。でも、それはNGで、とにかくコミュニケーションを取るべきは上司です。
「慣らし復帰期」には、「私も試行錯誤なので1、2カ月はバタバタしますけど、ヨロシク」と最初に言っておけば上司も心構えができるし、「まだ慣れてないけれど、将来的にはこう頑張っていきたい」「こういう働き方を実現したい」と、ことあるごとに言うようにすれば、「大変そうだけどモチベーションは下がってないんだ」と分かってもらえる。
業務量が増えてきて思うように両立が実現できない「泣きゴト期」に入った後も、「慣らし復帰期」にちゃんと上司とコミュニケーションが取れていれば、そこから脱出する的確なサポートをしてもらえます。
今、世の管理職のほとんどは、会社から「女性活躍」のミッションを与えられています。ワーキングマザーをマネジメントしろ、育成しろと上から言われているんです。
だから、コミュニケーションを取ってくる女性は間違いなくうれしい存在。育児や両立に疎い上司には、「働くママってこういうものなんですよ」「今はこれが主流なんですよ」なんて、ニコニコ言いながらあなた好みの両立スタイルを吹き込んじゃえばいいんです。
何も知らない男性が上司だなんて、ラッキーですよ?(笑)
本気で働くママになりたいなら
簡単に「時短」を選択しないでほしい

あと、私が声を大にして言いたいのは、育休復帰後も「簡単に時短を選択しないでほしい」ということ。時短っていったって、定時より1~2時間早く上がるというだけでしょ?
でも、そのたった1~2時間を優先したために、夫には「我が家の育児のメイン担当は妻なんだな」と思われるし、職場からも「家庭優先の働き方を希望しているのね」と認識されて、マミートラックに乗せられちゃう。
時短って、一見ワーキングマザーに配慮している制度のように見えるけれど、実際は、仕事への本気度を測られているようなものなんですよ。
今や多くの夫たちが、別に家事も育児もしないとは言っていない。でも、妻が「時短取ります」と言った途端に、「あ、やってくれるのね。ありがとう」となってしまう。それは当然じゃないのかな。自分が逆の立場だったら、やっぱりそう思うでしょう?
きついことを言うようだけれど、私は女性たちが「働く母は特別」と思い過ぎているんじゃないのかなと感じています。
子どもができたから、仕事は50%家庭も50%でワークライフバランス? それで一人前の戦力として扱ってもらいたいっていうのは違うと思うし、ワーキングマザーだからといって手加減された仕事ばかりをしていたら、不満がくすぶってくるのは当然です。
時短なんか取らないで、パートナーと協力して、仕事でも家庭でもお互いに100%の力を発揮できるように話し合うべきだと思うんですよね。
「仕事したい自分」をポジティブに受け止めて
面白い仕事をさせてもらう!
ただ、育休復帰後に不当な扱いをされて、「許せない」「悔しい」という気持ちを抱くことは、悪いことじゃない。
それは、「仕事が好き」という気持ちの裏返しだし、成長意欲があるということでもあるから。だから、そういった感情はネガティブにとらえずに、「ああ、私、仕事がしたいんだな」と素直に受け止めればいいと思います。
そして、そのことを上司にも伝えればいいんです。「課長、面白い仕事をさせてください」って。
もし、上司が打っても響かない人なら、その上の部長とか仕事のできる先輩とか元上司とか、とにかく分かってくれる人を求めて語り続ける。
「あいつ、本気で仕事をしたがっているぞ」と周囲に知れ渡れば、いずれ誰かが引っ張り上げてくれますから。
そういう意味では、これからワーキングマザーになる皆さんは、いざという時に力になってくれる人たちと今のうちにつながっておくといいと思います。
社内外に有効なアドバイスをしてくれる「コーチ」がたくさんいれば、育休復帰後もより早く「自走期」に移行できますしね。
そのためには、目上の人たちの印象に残るくらい、今のうちにちゃんと仕事をしておくことも大切だと思います。「あの子はこういうことができる」「あれをやらせたら上手」と覚えてもらえれば、コミュニケーションのきっかけも作りやすいでしょう。
仕事で充実感を味わいたいなら本気で仕事をするしかないんです。「仕事の報酬は仕事」。それは、子どもを産む前も生んだ後も変わらない真理だと私は思っています。
取材・文/阿部志穂 撮影/竹井俊晴







