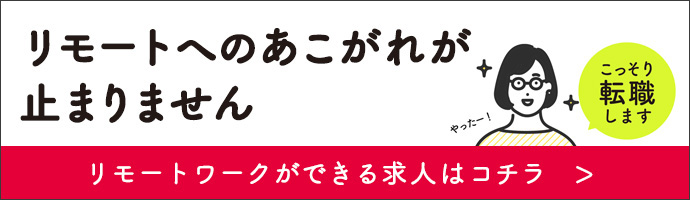「同僚がADHDかも…」大人の発達障害、自覚のない同僚にどう対応する? 職場でできる正しい対象法【脳内科医監修】

最近よく耳にする「大人の発達障害」「ADHD」という言葉。だけど、実際のところ、どういうものなのかよく分からないという人も多いのでは?
そこで5回に分けて、脳内科医の加藤俊徳先生が「大人の発達障害」の基礎知識をまるっとレクチャー。知っているようで知らない発達障害について理解を深めるべく、もややちゃんが聞いてきました!

【お話を伺った方】
脳内科医/脳の学校代表 加藤俊徳さん
脳内科医/医学博士/脳科学者。株式会社「脳の学校」代表。加藤プラチナクリニック院長。昭和大学客員教授。米国ミネソタ大学放射線科MR研究センターでアルツハイマー病や脳画像の研究に従事。発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。慶應義塾大学、東京大学などで脳研究後、2006年、株式会社「脳の学校」を創業。2013年、加藤プラチナクリニックを開設。発達障害やグレーゾーン、認知症などの診断・治療だけでなく、MRI脳画像を用いて社会人の脳が成長する脳トレ医療を実践。著書に『脳の強化書』(あさ出版)、『記憶力の鍛え方』(宝島社)、
『部屋も頭もスッキリする!片づけ脳』(自由国民社)、『脳とココロのしくみ入門』(朝日新聞出版)『ADHDコンプレックスのための“脳番地トレーニング”』(大和出版)、『大人の発達障害』(白秋社)などがある■X
「発達障害」ってどんなもの?
発達障害は、読んで字のごとく脳の発達過程に障害が見られること。特に「大人の発達障害」でよく見られるのは、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、自閉症スペクトラムの二つ。
AD(注意欠陥)とは、いわゆるうっかりとか忘れっぽいと言われるような症状のことで、仕事の面ではケアレスミスや整理整頓、時間の管理が苦手といった傾向が見られます。単におっとりしているタイプなのでは?と言われるような人も。
HD(多動性障害)とは、落ち着きがないと言われるような症状のことで、貧乏揺すりをしたり髪をいじったり、そういったクセがある人が多い。
「これくらいのことを大人ができないはずがない」その思い込みが大きなトラブルを招く
Part2で「20人に1人はADHD」というコメントがありました。となると、一緒に働いている人たちの中にもADHDなどの発達障害を抱えている人は多いと思います。
もし、職場の同僚にADHDの特徴がみられたり、発達障害の症状に困っていそうな人がいた場合、私たちはどう対応するのがいいのでしょうか?
一言で発達障害と言っても、その症状は千差万別です。ですから、まず大事なことは、相手は何ができないのか、きちんと把握すること。
相手が苦手なことを任せても失敗を生むだけです。逆に言うと、発達障害だからと言って、全く何もできないわけではありません。
何かしら得意な事柄はありますから、できないことと同じように、できることも把握・理解した上で、最適な業務を振り分けてみると組織運営にも支障が出ないようになると思います。
ここが少し難しいところですね。発達障害でなくても、人間であれば皆、得意不得意といった特性はありますもんね。
やりたくないこと、苦手なことは「やらなくていいよ」とはなかなか言いにくいこともあると思います。

その気持ちはよく分かります。とは言え、じゃあ相手ができないことを理解しているにもかかわらず、無理をして苦手な仕事を任せて、結果的にさらに大きなトラブルや被害を招いたとしたらどうしますか?
会社にとっても、あなたにとっても損でしかありません。
言われてみると確かに……。
会社員であれば、チームで仕事をしているという意識をもっと持てたらいいですね。一人の人が、完璧な存在になる必要なんて、正直ないんですよ。
皆それぞれ得意不得意があるんだから、得意なことにとことん取り組んで成果を挙げられるチームをつくったらいいと思います。そして、お互い、苦手分野を補い合うような関係を。そうすればお互いさまですよね。
多様な個性、特性を持った人たちが、それぞれの強みを活かしながら働く。これこそ、これからの組織のあるべき姿なんじゃないかと思います。
おお…まさにダイバーシティーですね。
一番やってはいけないのは、本人も周りも、「これくらいのことを大人ができないはずがない」と思い込んで、適性のない業務やポジションを振り分け、致命的なミスやトラブルを何度も引き起こしてしまうこと。
特性を生かした配置が、個々のパフォーマンスを最大化させるのは、発達障害がある人もない人も一緒です。
「大人の発達障害」は増加傾向。産業医が日本の企業に広まっていく必要がある
もう1つ気になるのが、発達障害の徴候は見られるけれど、本人に自覚がない、または治療の意思がない人についてどう対応するかです。
デリケートな問題ですし、本当に少しおっとりしているタイプなだけかもしれない。「ちょっと病院行ってきたら?」とは気軽に言い出せないですよね。
そうですね。ですから人事であったり、然るべきポジションの人から直接本人に伝えられるよう体制を築いていくことが、これからの組織の課題です。
私個人の意見としては、今後はもっと産業医が日本の企業に広まっていく必要があるのではないかと思いますね。

中途半端な知識しか持たない人事が勝手に判断してしまうのも危険ですしね。
そうですね。「できない」というのを、ただのわがままで言っているのか、そうでないのか、そこをよく見極める必要があります。
「大人の発達障害」との向き合い方が、少しずつ分かってきました。
Part1でお話しした通り、「大人の発達障害」は年々増加の傾向にあります。その中で発達障害を抱える人はどう組織の中で働くか。
そして周囲の人はどう発達障害を抱える人を受け入れ、共に働くか。
相互の理解を深め、発達障害を抱える人も健常者もお互いに働きやすい環境を整備していくことが、日本企業全体の経営課題と言えるでしょうね。
取材・文/横川良明
※この記事は 2018年7月25日に公開し2024年6月2日に更新しています