「自分の後悔を生かせたら」子どもの主体性を伸ばす“共感重視保育”を貫く『そらのいろ保育園』園長の信念
わが子に対して口をついて出てきてしまう命令口調の言葉。「やめなさい」「こうしなさい」「ダメって言ったでしょ」……。
幼いうちからしっかりルールを教えておかなければ……わが子の将来を思う母親としての小さな焦りから、つい、厳しい言葉を向けてしまうこともしばしば。でも、内心は不安を抱いている。「子どもへの接し方は間違っていないだろうか」「本当にこんな言葉ばかりでいいのだろうか」と。
品川区西品川にある「そらのいろ保育園」で園長として働く古岸瞳さんも、かつてはわが子の教育や子育てに悩んだ母の一人だった。

そらのいろ保育園
施設長 古岸 瞳さん
2児の母。保育士。事務、テーマパークスタッフ、企業受付などを経験した後、出産を機に専業主婦となる。第二子出産後の2015年、保育園運営企業にて社会復帰。現場で保育補助として経験を積み、園長補佐などを歴任。猛勉強の結果、保育士資格も取得。20年11月に社会福祉法人空のいろに入職し、22年4月よりそらのいろ保育園の施設長に就任
園長という職に就き、古岸さんはこう語る。
「幼少期に育まれる主体性や自立心を伸ばしていくために、大人ができる大切なことの一つが、子どもの考えや気持ちに共感すること」なのだ、と。
「子どもが幼いうちは、あれこれ先回りして大人が指示するより、子どもらしさに大人が共感することが最も大切」だと実感しているという。
保育方針に「共感重視保育」を掲げ、子ども自身の目線や気持ちを徹底的に尊重した園生活を提供している古岸さん。では、この「共感保育」は子どもの成長や発達にどのような成果をもたらすのだろうか。背景にある古岸さんの子育て経験とあわせて、具体的なビジョンを聞いた。
敷かれたレールの上でなく、自ら選んだ道を進めるような手助けを
長女を授かった時は専業主婦だったこともあって、大きくなるまでだいぶ手をかけて育てました。お受験をするご家庭が多い幼稚園でしたので、クラスの子についていけるようにと私も必死。おかげで長女は指示されたことはしっかりとできるようになりましたし、身だしなみもしっかり身についています。
しかし、振り返ってみて感じるのは「もっと自由にさせてあげればよかった」という後悔。
9年後、年の離れた次女を授かり、もう一度子育てができるとうれしく思いましたね。仕事もフルタイムで再開し、育児方針は放任主義へ急展開でシフトチェンジしました。仕事と家事の忙しさもありましたので、次女の言葉には「そうだね」「やってみていいよ」「自分でできたの!すごいね」と、応援するだけ。見守ることに徹底しました。
すると次女は、幼いうちから自分で考えて行動するようになっていったんです。
例えばある日、「画用紙がなくなったから、別のものにお絵描きしていい?」と聞いてきたので、深く考えもせずに「いいよ」と返事をしました。しばらくして見に行ってみると、なんと壁一面にクレヨンで絵を描いていたんですよ。
さすがにびっくりして、どうしてそんなことをしたのか聞いたのですが「ここに描いておけば、私の絵がいつでも見えてお母さんもうれしいでしょ?」って。私が子どもの絵をお家の壁に時々飾るのを見ていたのでしょう。この子にはこの子なりの考えがあるんだ、と気付かされました。
時には、こんなに自由な発想を受容してよいのかと戸惑うこともありましたが、今では私の想像を上回るくらい発想が豊かに育ち、たくさんのお友達に囲まれて過ごしています。言動も積極的で、活発です。育て方によって、幼少期の子どもの成長はこれ程までに変わるのかと驚きました。

子どもは大人の言動をよく見聞きしているので、大人が的確に指示を出せば、その通りに行動することができます。でも、それでは、いずれ誰かの敷いたレールの上で走ることが普通になってしまうでしょう。
しかし、この先の社会を生き抜いていくためには、指示に従う力だけではなく、望ましい行動を自ら選択する判断力、つまりは主体性や自立心を育む必要があると私は考えています。
ですので、そらのいろ保育園では、子どもたちの日常にあふれている一人一人の考えや気持ちに「共感する」ということを大切にしていきたいんです。
周りの大人が丁寧な対応を繰り返すことで、子どもは自身の考えや選択に自信を持てるようになります。この自己肯定感が積み重なり、卒園時には主体性や自立心が芽生えていく。結果、幼稚園や小学校に進学した際に、積極的に挙手したり、自信をもって意見を発言できる子に育っていると私は考えています。
みんなそれぞれ違っていい。少人数縦割り保育で実現する個性の伸ばし方
そらのいろ保育園では、1歳から5歳までの異年齢の縦割り保育を実施しています。1クラスたった8名、とっても少人数のクラス編成で入職当時は驚きましたが、私の信念とする「共感保育」ととても親和性が高いんです。
私の知っている幼稚園などは15人~30名程度の大人数クラス。先生と一度も会話をしないで一日を過ごす園児がいたりすると聞いたことも。それと比べて、そらのいろ保育園はたった8人なので担任の目がしっかり全員に届きます。一人一人の個性や、行動の速さ(遅さ)や、興味関心に気付き、寄り添いやすい保育環境です。
創作に興味を示す子どもがいれば、粘土や絵の具に触れる遊びを。歌ったり踊ったりすることに自分の特技を感じている様子があれば、音楽を使った活動を。全員に同じ遊びを強いるような活動方針ではなく、各担任がグループの子どもたちの興味や特性に合わせ、それぞれの可能性を刺激し、さまざまな才能を伸ばしていけるような日課や行事・イベントを考えて実行しています。
そのため、そらのいろ保育園の室内では、挨拶の歌、わらべ歌、ダンスの歌、アニメの歌など、いつもさまざまな歌が響き渡っています。ひな祭りやハロウィンなどのイベントごとに廊下に飾られる創作物も、グループごとに個性的なんですよ。
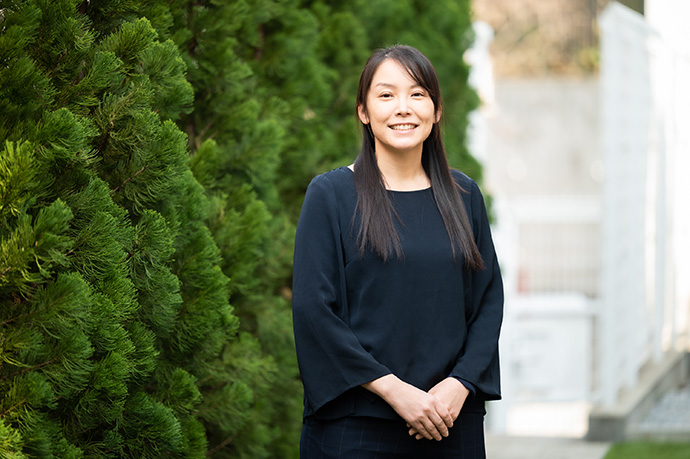
また、同じ年齢の子どもばかりの集団だと、「あの子はもう上手にお花が描けるのに、うちの子は全然できていない」というように、作品を見て保護者が子どもの出来不出来を比べてしまうことも少なくありません。みんなで同じように行動をすることが、子どものプレッシャーとなることもあります。一方で、異年齢の子どもの集団だと、できること・できないことがそれぞれにあることが前提となっているので競争を意識することがなくなります。
子どもにとって異なる年齢のお友だちとの関わり合いは、とっても刺激的。私たちは、子どもが自ら考えて行動を起こす様子を丁寧に見守り、必要に応じてそっとサポートすることを心掛けています。すると、大人の指示では出てこないような自由な発想を披露してくれることも。
わが家も、長女と次女は9歳の歳の差があります。長女が学校の宿題をしている横で、次女はけん玉をしている。そんな風景が日常茶飯でした。
子どもにとって保育園は「第二の家庭」。縦割り保育という保育環境は、私自身が経験してきた育児環境と同じ。縦割り保育の相乗効果はよく知っています。だからこそ、私が、この魅力を子どもたち、保護者の方、保育士や職員に伝えていく役目になったと思っています。
多くの子どもにとって保育園は長い時間を過ごす場所です。担任の顔色をうかがうことなく、子どもらしく、ありのままでいられる保育園であり続けたいと考えています。
園長は縁の下の力持ち。こども、保護者、保育士のつながりを大切に
また、そらのいろ保育園では、保護者の方の負担を減らすお手伝いにも力を入れています。
おむつはサブスク制を導入しているため、保護者はおむつを持参しません。また園服を準備してあるので着換えも不要。ほぼ手ぶらで登園を実現しています。保育園に来る時間も自由で、延長保育や土日祝の保育も行っています。いつお休みしてもいいように、行事などは一日限りではなく「運動会ウィーク」などと1週間かけて行うことで、期間中はいつでも楽しめるように工夫しているんですよ。
とにかく、親というのはみんな忙しい。私も同じく働く母なので、手間がかからないことや時間の融通が利くことのありがたさは身をもって知っています。だから、お仕事帰りの保護者さんにお会いする時には、笑顔で気持ちよくご挨拶をし、ご家庭の子育てを明るくするサポートをしています。

理想の保育園づくりというのは、私一人でできることではありません。日頃から子どもたちと向き合っている職員の協力があってこそ。これまで、さまざまなシーンで支えられてきました。
例えば、私も子どもの急な体調不良で仕事を休むことがあります。最初のころは申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、そらのいろ保育園の職員は、「大変でしたね。お子さん大丈夫ですか?」と、温かい言葉をかけてくれるんです。そのたびに救われるような気持ちになってきました。
だから私は、職員がアイデアを気軽に発言でき、のびのびと働けるような環境づくりのために笑顔でいる事を大切にしています。いつも優しく支えてくれる職員への恩返しのために。
理想は、関わる人すべてが笑顔でいられる保育園。保護者も、スタッフも、子どもたちも、みんな、たくさんの笑顔がはじける保育園であり続けたい。私は、これからも「縁の下の力持ち」として、誰よりもとびきりの笑顔で明るく元気に皆さんと関わっていきたいと思います。
園長を支える名バイプレーヤーの役割
【地域活動の経験を生かし、行政と連携した保育現場の実現を(園長補佐 杉本将輝さん)】

そらのいろ保育園
園長補佐 杉本将輝さん(ショーグン)
2児の父。大手SIerでエンジニアとして勤務する傍ら、子どものための地域活動に参加。2020年そらのいろ保育園に入職。保育士資格取得に向けて勉強中。子どもたちからは「ショーグン」の愛称で親しまれている
わが子が通う学校のPTAで会長を務めたことをきっかけに、地域の子どもたちのためになる活動に注力するように。一般社団法人やNPO法人の事業に参画して、行政の協力を得ながらさまざまな遊びや学びの場づくりに励んできました。今後はより子どもたちの支えになれるような仕事をしたいと考えてキャリアチェンジを決意し、そらのいろ保育園に入職しました。
そらのいろ保育園で展開する縦割り保育(異年齢のグループ)で生活する子どもたちの成長には目を見張るものがあります。特に一番年上の5歳児になると、こちらが頼まずとも保育士や年下の子のお手伝いをしてくれるんです。
年下の子のお散歩や食事の準備を手伝ってあげている光景は日常茶飯事。人に対する思いやりが育まれている様子がよく分かります。
子どもの個性は一人一人異なります。障害がある子、病気を抱えている子、活発な子、おしゃべりな子などいろいろです。また、子どもを育てる家庭の状況もさまざまです。そらのいろ保育園は、あらゆる立場の子どもや家庭に寄り添っていける園を目指しています。
【複雑な家庭環境やハンディキャップのある方へのケアを通じて、園長をサポートしたい(事務長 石 絵美さん)】

そらのいろ保育園
事務長 石 絵美さん
2児の母。そらのいろ保育園事務長。キャリアコンサルタント。出産を機に、働くママや子育てに悩む保護者を応援したいとの思いから保育業界へ。保育園の運営管理、園長指導の他、メンタルヘルスマネジメントに従事。業務上の悩みや、働き方ライフワークバランスなどの相談役
古岸園長は、一人一人の子どもに対する「共感」を重視しているように、一緒に働くスタッフの気持ちも尊重してくれる人です。職員一人一人に寄り添い、多様な意見が反映された柔軟性のある保育現場づくりができています。
私の役割は、職員がいきいきと働ける環境を整えることです。園長だけでは解決できない職員トラブルや、苦情の対応をしたり、離職を考えている職員の話を聞いたり、クレームを出してしまった職員を指導したり、上手に保育ができないと悩む職員に保育技術を助言したりして保育園を支えています。
ハンディキャップのある子、そうでない子、家庭環境にトラブルを抱えている子など、さまざま子どもが保育園に通っているように、職員一人一人もさまざま。それぞれに悩みや不安を抱えながらそらのいろ保育園という一つの場所で働いています。
職員自身の心が軽くなることで、仕事にゆとりと笑顔があふれ、園内の雰囲気が明るくなる。すると、子どもたちにとっても過ごしやすい保育園が実現すると考えています。また保護者にとっても気軽に子育て相談ができるようにしたいです。そらのいろ保育園に通わせたい!と地域の方に選ばれ続ける保育園でありたいと思っています。
>>そらのいろ保育園の詳細はこちら
>>そらのいろ保育園(社会福祉法人空のいろ)の求人情報はこちら
取材・構成/瀬戸友子 撮影/吉永和久 編集/栗原千明・秋元祐香里(ともに編集部)





