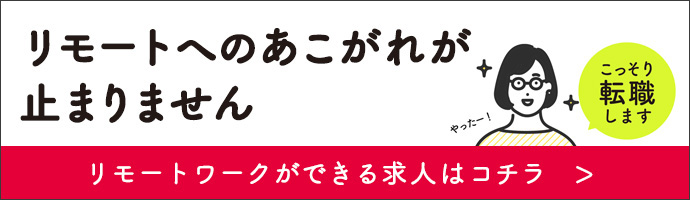【例文・テンプレあり】好印象な退職挨拶って?スピーチ・メール・手紙・SNSなど手段別に紹介

無事転職先が決まり、業務の引き継ぎもそろそろ終盤……となると、次に頭を悩ませるのが「退職挨拶」ではないでしょうか?
この記事では「お世話になった人に感謝の気持ちをしっかり伝えたい」「好印象のまま退社したい」と考えている女性に、退職挨拶のマナーとポイントを紹介します。
スピーチ・メール・手紙など、手段別の例文・テンプレもあるので、ぜひ活用してください。
退職挨拶の基本的なマナーとポイント

退職挨拶をする時は、口頭で直接伝える方法もあれば、メールや手紙などで伝える方法もあります。
まずは、どんな手段の時でも心得ておきたいマナーやポイントを紹介します。
【退職挨拶のタイミングは上司と相談する】
退職の意思を上司に伝え、退職日が確定しても、すぐに同僚に話すのはマナー違反です。不用意に知らせてしまうことで職場の士気に影響することも考えられますので、会社の発表を待つのが賢明です。
引き継ぎなどの関係で会社の発表前に伝える必要がある際は、事前に上司に相談して許可を取るようにしましょう。
【退職日を報告する】
退職挨拶をする際は、「本日付で」「○日付で」など、退職日を明確に伝えるようにしましょう。
引き継ぎなどをいつまでにおこなえば良いか、いつまで業務用のメールアドレスに連絡ができるかなどが分からないと、相手に余計な負担がかかってしまうからです。
特に退職日まで余裕がある場合は必ず記載することを忘れてはいけません。
【退職挨拶では感謝を伝える】
退職挨拶は感謝の気持ちを伝えるためのものです。ネガティブな理由での退職だったとしても、これまでお世話になった人がいることには変わりありません。
退職間際の余計なトラブルを避けるためにも、気持ちよく去ることを心掛けましょう。
【詳細な退職理由は言わない】
退職挨拶の際は、詳細な退職理由に触れる必要はありません。
プライベートに関わることですし、思いがけずネガティブな印象を抱かれてしまう可能性もありますので「一身上の都合で退職することになりました」程度の記載でOKです。
結婚などポジティブな理由による退職であれば、親しい間柄の人に伝える分には問題ありません。
【恨み言や不満は言わない】
退職挨拶で「会社に不満を伝える最後のチャンス」とばかりに恨み言をつづるのはよくありません。
これからもその職場で働く人たちに対して失礼にあたりますし、あなたの信頼を落とすことにもなりかねないからです。
職種や業界によっては、昔の職場と一緒に仕事をする関係性になることも珍しくありません。将来の自分が不利になることがないよう、最後まで丁寧な対応をするようにしましょう。
【スピーチ編】退職挨拶のマナーやポイント
退職日の朝礼や夕礼、退社後の送別会などで退職挨拶を求められた際のマナーやポイントについて紹介します。
最後に例文・テンプレもありますので、ぜひ参考にしてみてください。
【スピーチ編】好印象な退職挨拶のポイント
スピーチで好印象な退職挨拶をするには、以下の四つのポイントがあります。一つずつ解説します。

【入社時のエピソードや失敗談を盛り込む】
そのときの状況や立場などにもよりますが、退職挨拶のスピーチは基本的に社内向けにおこなうことが多いため、多少砕けた内容でもOKです。
入社時に苦労したことや失敗談を話すことで親しみやすさやユニークな人間性を伝えることができるでしょう。当時の上司の名前を出して感謝を伝えるのもおすすめです。
当時を知る同僚や上司にとってはクスッと笑える内容でしょうし、後輩には「誰にでも新人時代はあったのだな」と勇気を与えるかもしれません。
【会社での学びや得たことを具体的に話す】
先ほども述べましたが、退職挨拶は感謝の気持ちを伝えるものです。会社で学んだことや得たことなど「この会社に入社して良かったこと」を具体的に語るようにしましょう。
残された人たちは自分の会社の良さを再確認でき、あなたに対しても好意的な気持ちを抱いてくれるはずです。
【長くなりすぎないよう、簡潔に収める】
朝礼や夕礼など業務中に退職挨拶の時間をもらう時は、長くなりすぎないように注意が必要です。上記の内容を含めつつ、長くても3分程度に収めるとちょうどいいでしょう。
【タイプに応じて台本を用意してもOK】
冒頭でも述べたように、社内向けのスピーチであればそれほどかしこまらなくても大丈夫ですので、スラスラ話せなくても、気持ちを込めて伝えることが大切です。
「大勢の人の前でうまく話せるか自信がない」という人は台本を用意してもいいでしょう。その際は「緊張してしまうので、カンペを用意しました」などと一言添え、事務的な印象にならないよう心掛けると好印象となります。
【例文】好印象な退職挨拶/スピーチ編
新卒で入社し、最初は電話の取り方すら分からず戸惑うことばかりでしたが、チームの皆さまのサポートのおかげで、少しずつ業務に慣れることができました。
特に○○さんには、たくさんのアドバイスをいただくと同時に、さまざまなことにチャレンジさせていただき、仕事の楽しさに気付くことができました。ありがとうございます。
この会社の良いところは、やはり「人」だと思います。これからどこでどんな仕事をすることになっても、皆さまに教えていただいたことを活かしていきたいと思います。
短い間でしたが、本当にお世話になりました。皆さまのご活躍とご健康を心よりお祈りしております。
【例文】好印象な退職挨拶/一言スピーチ編
新卒で入社してから○年、皆さまにはたくさんのご指導をいただき、心より感謝しております。 退職後も、ここでの経験を胸に頑張っていきたいと考えております。
最後になりますが、皆さまのご活躍とご健康を心よりお祈りしております。 本当にありがとうございました。
【メール編】退職挨拶のマナーやポイント
そもそもメールでの退職挨拶はマナー違反?
退職の挨拶は、基本的には直接会って口頭でおこなうのが基本ですが、社員数が多い会社や取引先など、退職日までにどうしても会うことが難しい場合はメールでおこなうのもマナー違反ではありません。
ただ、人によっては事務的なメールのみで退職挨拶をするのは失礼だと感じる方もいるため、その人のタイプや関係性などによって対面・メール・手紙を使い分けるなど工夫が必要です。
また、メールでの退職挨拶は、文面によっては事務的なイメージを与えてしまうため注意が必要です。メールならではのマナーもありますので、ぜひおさえておきましょう。最後に例文・テンプレも紹介します。

【メール編】好印象な退職挨拶のポイント
メールで好印象な退職挨拶をするには、以下の五つのポイントがあります。一つずつ解説します。
【一目で退職挨拶だと分かる件名にする】
メールで退職挨拶をする際は、他のビジネスメールと区別できるよう、一目で退職挨拶だと分かる件名にしましょう。
社内に送る際は「退職のご挨拶【部署名 名前】」、社外に送る際は「退職のご挨拶【社名 名前】」などのようにするのがおすすめです。
【メールでの挨拶になった旨を本文で一言記載する】
先ほど「直接会って退職挨拶をすることが難しい場合はメールでおこなうのも有効」とお伝えしましたが、その際は文中で「本来であれば伺ってご挨拶すべきところ、メールでのご挨拶となったことをお詫び申し上げます」など一言添えると好印象です。
【取引先に一斉送信する場合は各送信先をBCCに設定する】
送信先が多い場合は一斉送信でもマナー違反にはなりません。
ただし、通常のビジネスメールを送信するときのように「CC」を使うと、メールを送った方全員のメールアドレスが開示されてしまうため、「BCC」に設定するようにしましょう。
ちなみに、「TO」には自分のメールアドレスを設定するのが一般的です。
【メールを送るタイミングに気をつける】
退職挨拶のメールは早すぎても遅すぎても相手に迷惑をかけてしまいます。社内向けと社外向けでそれぞれ適切なタイミングが異なるため、注意しましょう。
一般的に、社内向けにメールを送る際は、最終出社日の退社2-3時間前が理想的です。社外に送る際は業務の引き継ぎが始まったタイミングでなるべく早く送るようにしましょう。
心配な方は直属の上司に相談し、指示をあおぐのがおすすめです。
【署名の連絡先は私用のメールアドレスにする】
基本的に、最終出社日に退職挨拶のメールを送る際は署名に社名や業務用の連絡先は記載しないのがマナーです。
最終出社日を過ぎるとメールアドレスが使用できなくなることもあるため、署名を見て連絡してくれた人がいてもエラーとなってしまうからです。
特別親しくしていた人など、退職後も連絡を取り合いたい場合はプライベートの連絡先を記載しておくと良いでしょう。
【例文】好印象な退職挨拶/メール編
メールで退職挨拶をする際の文面を社内向け/社外向けに分けて紹介します。
退職挨拶メール/社内向け
お疲れさまです、〇〇部の〇〇です。
突然のご報告となりますが、一身上の都合により本日付で退職することとなりました。
本来であれば直接ご挨拶すべきところですが、
メールにて失礼いたします。
入社して〇年、皆さまには大変お世話になりました。
至らぬ点も多々あったかと思いますが、
皆さまのご指導やフォローに支えられて多くのことを学ばせていただきました。
今後も、ここでの経験を生かしていきたいと思います。
明日以降の連絡先は下記のとおりです。
メールアドレス:◯◯◯@◯◯◯.◯◯◯
携帯:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
最後になりましたが、皆様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
今まで本当にありがとうございました。
退職挨拶メール/社外向け
株式会社○○ ○○部
○○○○様
平素より大変お世話になっております。
株式会社○○の○○です。
突然のご報告となり大変恐縮ですが、
○月○日をもちまして○○社を退職することとなりました。
○○様には入社時からお付き合いさせていただき、たくさんのご指導、ご協力をいただきました。
短い間ではございましたが、心より感謝申し上げます。
引き継ぎは、後任の○○へ行っております。
後日改めて○○よりご連絡させていただきます。
後任者名:○○部 ○○○○
メールアドレス:◯◯◯@◯◯◯.◯◯◯
携帯電話:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
今後とも弊社と変わらぬお付き合いのほど、何卒よろしくお願いいたします。
末筆ながら、○○様のご活躍をお祈りいたします。
【手紙編】退職挨拶のマナーやポイント
退職挨拶を手紙で送る際のマナーやポイントについて紹介します。最後に例文・テンプレもありますので、ぜひ参考にしてみてください。
【手紙編】好印象な退職挨拶のポイント
手紙での退職挨拶は、メールよりも丁寧な印象を持ってもらえ、比較的年配の方に好まれる連絡方法でもあります。
手紙で好印象な退職挨拶をするには、以下の二つのポイントをおさえましょう。最後に例文・テンプレもありますので、ぜひ参考にしてみてください。
【手紙のマナーを守る】
手紙で退職挨拶をするときは、手紙特有のルールを守るように気をつけましょう。具体的には、以下のようなルールがあります。
・頭語「拝啓」、結語「敬具」を入れる
・前文に時候の挨拶を入れる
・本文には「さて、私議~」「さて、私こと~」を入れる
【印刷よりも手書きがベター】
手紙を送る相手が多い場合は印刷で作成しても問題はありませんが、誠意をしっかり伝えるには手書きで作成するのがベターです。
特に年配の方は手書きの手紙が好まれることが多いです。手書きで作成するのは大変ですが、退職後も付き合いが続く可能性がある方などには手書きにしてみてはいかがでしょうか。
【例文】好印象な退職挨拶/手紙編
○○の候 ○○様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、私儀
○月○日をもちまして○○株式会社を退職することとなりました。
在職中は公私ともに格別のご厚情を賜り、心から御礼申し上げます。
書面をもって失礼とは存じましたが、お礼かたがたご挨拶申し上げます。
末筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
敬具
令和○○年○月○日
東京都○○区○○ ○-○-○(住所)
○○○-○○○○-○○○○(携帯電話)
○○○○(名前)
【SNS編】退職挨拶のマナーやポイント
転職する人が増えたことやSNSの普及などにより、近年は退職の報告および今後のキャリアについてブログやSNSなどで発信する、いわゆる「退職エントリ」をする人も増えました。
退職エントリは一歩間違えると読んだ人に「横柄な人」という印象を与えたり、退職した企業を批判しているように見えたりしてしまうため、注意が必要です。
SNSで退職挨拶をする際のマナーやポイントを二つ紹介します。
【批判やマウントにならないように気を付ける】
退職エントリには決まった形式はありませんが、退職の報告やこれまでのキャリアの変遷、実績、今後のキャリアなど書くケースが一般的です。
退職した企業の内部情報や機密情報などが書かれていない限り大きなトラブルにはなりにくいと思いますが、退職した企業に対する不満にもとれるような内容が書かれていたり、自分一人で成果を上げたような書き方がされていたりすると、読んだ人に良い印象は与えません。
身近な人とのみつながっているSNSであっても、いつ誰がその投稿を見ているか分かりません。思わぬトラブルを招いたり、悪印象を抱かれたりしないためにも、感謝の意を伝えるような内容に終始するのが賢い選択と言えるでしょう。
【退職エントリに書かれるトピック】
先ほども述べたように、退職エントリには決まった形式はありません。基本的には普段SNSを利用する時と同様に書きたいことを自由に書けますが、転職エントリに書かれるトピックとしては以下のようなものがあります。
・退職の報告
・退職することになった経緯
・入社からこれまでのあゆみ
・会社で経験してきたこと、身に付けられたこと、実績
・会社での思い出
・退職後の進路、次なる目標
・周囲の人への感謝の気持ち
退職挨拶に関するよくある疑問
退職挨拶に関するよくある質問をまとめました。当てはまるものがあれば参考にしてみてください。
【退職の挨拶はどの範囲までするべきですか?】
退職の挨拶は、あくまでもお世話になった人に感謝の気持ちを伝えるものです。自分がお世話になった・日ごろから関わりのある人であれば全員が対象と考えるべきでしょう。
かしこまった形でなくとも、ランチ時などに伝えるという方法もありますよ。退職後も付き合いを続けたい人がいれば、ぜひこの機会にコンタクトを取ってみるのもいいのではないでしょうか。
【退職時にお菓子などは配るべきですか?】
必須ではありませんが、ちょっとしたギフトと共に感謝の気持ちを伝えたらきっと喜んでもらえるはずです。大人数分用意するのは大変ですので、同じ部署やチームの人数分など無理のない範囲で用意するのがいいでしょう。
その際は常温保存でき、日持ちがする焼き菓子などが鉄板です。個包装されているものだとなお良いでしょう。
【チャットツールで退職挨拶をするのはアリですか?】
くり返しにはなりますが、対面で退職挨拶をするのがもっとも丁寧な方法です。
とはいえ、リモートワークメインの働き方だったり、フランクな会社だったりする場合はチャットツールで退職挨拶をしても失礼にはあたらないでしょう。職場の雰囲気や慣習に応じた手段を使うのが無難といえます。
【パートでも退職挨拶は必要ですか?】
シフト制で働いている場合、最終出社日に会えない人もいるでしょう。また個人のメールアドレスがない場合もあるため、必ずしも一人ひとりに退職挨拶をしなければならないとは言えません。
シフトが重なった日などにその都度感謝の気持ちを伝えるのがいいでしょう。またパート先によっては独自の慣習があることも珍しくないため、上司や先輩などに聞いておくのが得策です。
まとめ|退職時の挨拶は一つのけじめ。マナーを守り気持ちのいい挨拶を
退職挨拶は在職中にお世話になった人に感謝の気持ちを伝える絶好の機会であり、同時にあなたの印象を決定づけるものでもあります。
仮に退職の理由がネガティブなものだったとしても、自身のけじめとしてきっちり退職挨拶をすることはきっとプラスになるはず。次の職場に向けて前向きにスタートを切るためにも、気持ちのいい退職挨拶を心掛けましょう。
文/赤池沙希