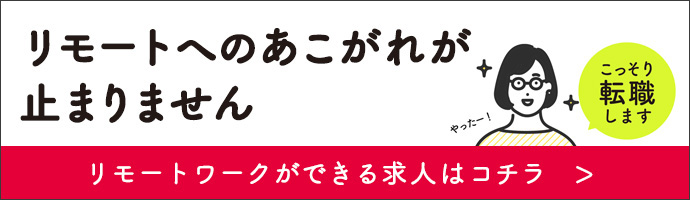管理職女性の悲痛「発達障害グレーゾーン部下のせいで病みそう…」職場でできる適切な対処法とは【公認心理師・舟木彩乃さん】

「うちの部下、絶対に発達障害だと思うんです」
部下の発達障害を疑い、カウンセリング室に駆け込む上司が増えているーー。
そう話すのは、ストレスマネジメントの専門家で公認心理師の舟木彩乃さん。
医師から発達障害だと診断されているわけではないけれど、発達障害の傾向がある……そんな「発達障害グレーゾーン」な人々に悩まされる人からの相談が増加傾向にあるという。
女性管理職の方からも、
「同じミスを繰り返す部下に困り果てている」
「遅刻を繰り返す人に、どう注意すればいいか分からない」
「指示を守れない部下への対処に終われて、自分が壊れてしまいそう」
など、さまざまな相談が寄せられています。
職場で「発達障害グレーゾーン」な人のマネジメントに迷った場合、どう対処すればいいのだろうか。

ストレスマネジメント専門家、公認心理師
舟木彩乃さん
一般企業の人事部で働きながらカウンセラーに転身、その後、病院(精神科・心療内科)などの勤務と並行して筑波大学大学院に入学し、2020年に博士課程を修了。著書に『「首尾一貫感覚」で心を強くする』(小学館)、『過酷な環境でもなお「強い心」を保てた人たちに学ぶ「首尾一貫感覚」で逆境に強い自分をつくる方法』(河出書房新社)、近著に『「なんとかなる」と思えるレッスン』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『発達障害グレーゾーンの部下たち』(SBクリエイティブ)などがある(X:@funakiayano)
「発達障害かどうか」は重要ではない
ーー「部下が発達障害かもしれない」という相談が増えているとのこと。それはなぜなのでしょうか?
「発達障害」という言葉が多くの人に認知されるようになり、偏ったイメージがひとり歩きしている状態なのではないかと思います。
例えば、カウンセリングにいらっしゃる上司の方はよく、部下の方の次のような行動に困っていると話します。
・考え方が極端でデジタル思考
・こだわりが強く頭が固い
・すぐ感情的になる、パニックを起こす
・暗黙の了解ということが分からない
・コミュニケーションがうまくとれない
・なくしものや忘れ物が多い
・遅刻を繰り返す
・集中力がない
などなど……
いずれも、「同じことを何回も指摘したけれど直らないから、発達障害だろう」と言うのです。
ーー確かに、これらの内容を見ると「発達障害かも」と言いたくなる特徴ばかりですね。
はい、先ほど挙げた内容が発達障害の特徴の一つであることは間違いありません。
ただ、これらの特徴があるからといって、その人が発達障害だと断定できるものではないんです。
そもそも発達障害とは単一の疾患ではなく、「自閉症スペクトラム障害(ASD)」や「注意欠如/多動性障害(ADHD)」などの障害の総称。職場の発達障害に関する相談で圧倒的に多いのは、このASDとADHDの二つです。
発達障害かどうかは、医療機関が問診や検査などを行って総合的に判断するものなので、一般の人が簡単に見分けられるものではありません。
仮に「自分は発達障害かもしれない」と思って病院に行っても、「発達障害の傾向がありますね」「グレーゾーンですね」などと言われてしまい、はっきりした診断名がつかないケースも多いんです。

ーー発達障害かどうかは、それくらい見分けがつきづらいものなんですね。
はい。ただ、上司の方は「自分の部下が発達障害かどうか知りたい、はっきりさせたい」とよく仰るのですが、正直に言って、それはあまり意味がないと思うんです。
ーーなぜですか?
もちろん、発達障害の特徴を管理職としてしっかり学ぶことは大事です。
ですが、発達障害は先天的なもので、周囲の人が治してあげられるものではないし、当事者が努力したところで限界があります。
もしも管理職にできることがあるとすれば、その人の特性を生かすポジションに配置したり、苦手なことをチームでカバーできるような体制をつくったりすることです。
でも、これは相手が発達障害かどうかにかかわらず、管理職が部下の能力を最大限引き出すためにやるべき仕事ですよね。
そういう意味では、部下が発達障害かどうかを知ることは必ずしも重要ではなく、一つ一つの問題に対処していくしかないのかなと思います。
環境が変われば、部下も変わる

ーーとはいえ、発達障害だと診断されていないのに部下がミスや遅刻を繰り返したり、不躾な発言を繰り返したりしている場合、「なまけているだけではないか」「悪意があるのではないか」と疑ってしまいそうです。
その気持ちもよく分かるのですが、実際はどうあでれ、基本的には「相手に悪意はない」ものとして受け止めた方がいいです。
「相手に悪意がある」という前提で接してしまうと、人間関係がどんどんこじれて収拾がつかなくなってしまいます。
「部下が発達障害かもしれない」とカウンセリングにいらした方の中でも、かなり多くの人がこの状態になってしまっていました。
ーーこういう場合も、相手に悪意があろうとなかろうと、「起こっている問題」にどう対処するかだけを考えた方がいいと。
その通りです。
例えば、相手に悪意がなかったとしても、何度も同じことを指摘するのは誰だってつらいし、自分の努力が報われなければ嫌な気持ちになるものです。
ですから、なるべくマネジメントに感情は持ち込まず、「管理職の仕事」だと割り切って淡々とやることが大事。
あとは、発達障害グレーゾーン部下の環境を変えてみるのも一つの手です。

ーー環境を変えるというのは?
これはあくまで一例なのですが、以前カウンセリングに来てくれたAさんの事例を紹介します。
ある企業の研究職として入社したAさんは、とても優秀で高い成果をあげていたので、比較的はやい段階で管理職に抜擢されました。
すると、仕事に全く集中できなくなり、欠勤や遅刻が増え、勤怠が乱れるようになってしまったのです。
困ったAさんが病院に行くと、「ASDの傾向があると言われた」とのこと。
管理職になって急に仕事内容が変わり、部下や外部の人とコミュニケーションをとる仕事が増えた結果、AさんのASD傾向が顕著になったのです。
これは、職場は同じだけど、担当する業務が変わったことでストレス過多になり、環境に適応することができなくなってしまったパターン。
この事例からも分かる通り、得意分野で強みを発揮できるような業務を中心にしている場合は、発達障害グレーゾーンの部下は非常に高い成果を上げられるかもしれません。

また、物理的に環境を変えることが有効な場合もあります。
例えば、集中力がなかったり、注意欠陥多動の傾向があったりするタイプの人なら、思い切って静かな環境で仕事ができるようにしてあげてもいいかもしれません。
いつもキョロキョロ、そわそわしているようなら、「どんな環境なら落ち着いて働けるか」を本人に聞いてみてもいいでしょう。
発達障害の人の中には、「絶対に窓際に座りたい」「ドアの近くは嫌だ」など場所に強いこだわりがある人もいます。業務に支障が出ないなら、そうした希望を汲んであげるだけで本人も働きやすくなるかもしれません。
「ここまで配慮してあげなければいけないの?」と思うかもしれませんが、感情はいったん脇に置いておき、仕事で成果をあげてもらうことを最優先で考えることが、合理的な判断とも言えます。
自分の心を守ることが最優先

ーー発達障害グレーゾーンの部下の問題については、感情ではなく合理性で判断することが重要ですね。
はい。そして、部下の行動に困っているなら、それを一人で抱え込まないことも大事です。
女性で管理職になったばかりの人だと、「自分でどうにかしないといけない」「ちゃんとやらなくちゃ」と考えているうちに、自分自身が病んでしまうケースも少なくありません。
そうならないためにも、チームメンバーに協力をあおぎ、みんなで面倒を見てあげるようにしましょう。
人と人の相性もありますから、「この人が対応するとうまくいく」というパターンが見つかるかもしれません。
ーーメンバーに迷惑をかけたくなくて、「自分で全部対処しよう」と思ってしまう人も多いかもしれませんね。
そうなんです。でも、そこはもう持ちつ持たれつでやるのが一番です。
せっかく会社から信頼されて管理職になったのに、自分が心を病んで退職するようなことになってしまっては、もったいないですからね。
「自分の心を守る」ことを一番に考えていいと思います。
それと関連して、「体調の悪いときや、気分が悪いときに、イライラする相手に近づかない」ことも大事です。
ーーなぜですか?
いつも以上にストレスを感じやすくなり、心身に与える影響が大きくなってしまうからです。
普段なら淡々と受け流せることでも、体調が悪いときはついかっとなってしまい、相手に感情をぶつけてしまう可能性が高くなります。
発達障害の人の中には、繊細ゆえに他者の感情を過度に読み取ってしまったり、感情のコントロールが苦手だったりする人も多いため、あなたの発言に対してかっとなって言い返してきたり、激昂したりする人がいるかもしれません。
すると問題が大きくなって余計な負担になりますから、自分が不調なときはなるべく深く関わらないようにして、余裕があるときにしっかり対応すればいいと思います。
ただし、発達障害グレーゾーンの人だけを避けるような態度はとらないよう注意しましょう。
うまくマネジメントできなくて当たり前

ーー今後、管理職になる女性にとっても、発達障害の正しい知識を身につけることは大事ですね。
はい。本来であれば発達障害に関する正しい知識を管理職の方や、その候補者の方は身につけておくことが望ましいのですが、実際にはほとんどの人が専門的な研修等を受けないまま管理職になっています。
そして、現場でさまざまな問題に直面し、その対処を迫られているという印象です。
でも、発達障害は複雑かつあいまいなものなので、マネジメント経験が浅く、この分野のことを学んだこともない人が個々に対応するには、あまりに難しい問題。最初から一人でうまく対処できなくて当たり前なんです。
ですから、発達障害グレーゾーンの部下をうまくマネジメントできなくても、自分を責める必要はありません。これは、職場全体の問題です。
もしも課題にぶつかったら、自分だけでトラブルを抱えずに、上司や人事部門の人などに困りごとを相談してみてください。社内に健康管理室などがあれば、産業医や保健師、カウンセラーなどに相談することも検討しましてみましょう。
さらに、発達障害グレーゾーンの部下を「変えよう」と思うと、たいていうまくいきません。相手も反発してお互いの関係が壊れてしまう可能性があります。
ですから、その人自身を変えるのではなく、起きている問題にどう対処するかに目を向けることをおすすめします。
あなた自身が元気でいることが、チームのメンバーにとっても、職場にとっても何より大切なこと。自分の心の健康を、第一に考えてくださいね。
【書籍紹介】
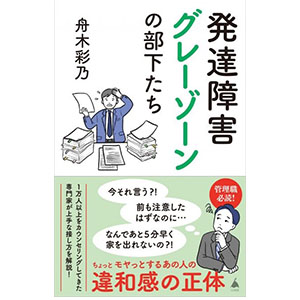
『発達障害グレーゾーンの部下たち』(著者:舟木彩乃)
>>書籍詳細
取材・文/栗原千明(編集部)