「象、死んだ魚、嘔吐」で相互理解を促進!? 専門性の高いチームを率いるマネジメントのコツ/LayerX
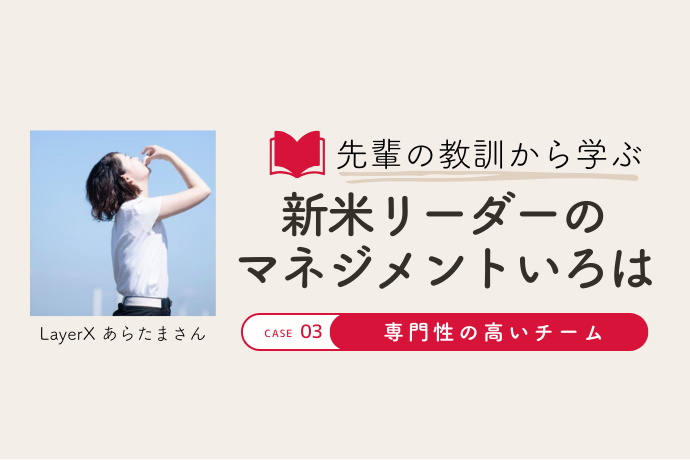
女性管理職登用に注力する企業が増加し、リーダーや管理職に任命される20、30代の女性も増えてきた。しかし、会社から抜擢されても「スキルも経験も足りないのに、私が管理職なんて……」と不安に感じてしまうこともあるだろう。
そこで今回は、急成長中のベンチャー企業3社の女性マネージャーにインタビューを実施。彼女たちの失敗談や、経験から得たマネジメントノウハウの中から、新米管理職が今すぐに実践できる教訓を学んでいこう。
今回お話を聞いたのは、AI SaaS事業『バクラク』を手掛けるLayerXで申請・経費精算プロダクトのエンジニアリングマネージャーを務める新多真琴(あらたま)さん。
前職ではスタートアップでCTOを務めていたが、当時はマネジメント未経験からのCTO就任だったというから驚きだ。
現在はエンジニアのピープルマネジメントとプロダクトマネジメントの両方を担っている彼女。専門性の高いエンジニア組織を、一つにまとめるためにあらたまさんが心掛けてきたこととは?

LayerX バクラク事業部 エンジニアリングマネージャー
新多真琴(あらたま)さん
国立音楽大学を卒業後、DeNAでソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタート。その後はセオ商事、ロコガイドを経て、Cake.jpにて執行役員CTOを務めた。現在はLayerXにて「バクラク申請・経費精算」のEMを担いつつ、コミュニティ「EMゆるミートアップ」を運営中。趣味は全国津々浦々のサウナ探訪。「日本もちもち協会」代表。X/note
「チームをうまく活かしたい」マネジメント未経験でCTOに
——あらたまさんはもともとスタートアップでCTOをされていたんですよね。でも当時、マネジメント経験はなかったとか。
はい。オファーを受けたことがきっかけで、実践の機会を飛ばしてCTO候補として転職しました。
もちろん大きな不安もありましたが、周りの先輩や他社のCTOなどに相談したら「いけると思うよ」と言われ、「この人たちが言うんだったらいけんのかな」って(笑)
実際に、マネジメントのインプットを続けながらなんとか乗り切ることができました。もともとチームをうまく活かして成果を上げたいタイプだったこともありますね。
——転職して、現在はどのようなポジションに?
今はAI SaaS『バクラク』の申請・経費精算プロダクト開発を担うチームのマネージャーをしています。
エンジニアのピープルマネジメント、そしてPdM(プロダクトマネージャー)とタッグを組んで、プロダクトの行く末を決めていくような役割も担っています。
——エンジニアの組織は、女性比率が低い企業も多いですが、LayerXはいかがですか?
現在のチームはメンバーに女性もいますが 業界全体のエンジニアの女性比率自体が少ないのは確かですね。勉強会などに出向いても、女性は少ないですし。
でも基本的にエンジニアって性差の表れにくい職業の一つなので、特段意識することはありません。
メンバーの「弱み」を指摘して気付いたこと

画像はイメージ(以下同)
——マネジメントをする中で、失敗や後悔していることはありますか?
前職で、すごく突破力のあるメンバーがいたんです。課題を見つけると、すぐに関係者に「ここ、困っていませんか?」と聞きに行って課題を掘り下げるような、勢いのあるメンバーで。
ただその素晴らしい行動力は、裏を返すと、細かいことを忘れがちだったり、行動する前にリスクを検討せずに突っ走ってしまったりする危うさもあったんですよね。
そこで私は、「突破力があるのは素晴らしいけれど、その副作用を考えられないまま走りだしてしまうと、あとで問題になるかもしれないから、少し気を付けた方がいいのでは」とフィードバックしました。
そしたらそのメンバーは、細かなことに気を付けようとするあまり、持ち前の突破力を発揮できなくなってしまったんです。
——弱みを意識するあまり、強みまで薄れてしまったと。
はい。そのときに、人の強みには同じぐらい弱みを生む可能性があって、その弱みは必ずしも「本人が克服すべき課題」として捉える必要はないということに気付きました。
私たちはチームで仕事をしているので、チームとしてカバーし合うことが大切です。
例えばその人によってチームに突破力が生まれているのであれば、その過程で取りこぼしてしまいそうなところに対してあらかじめ手を打てるような気質の人を合わせるなど、チームとしての良さを生かす工夫が、マネージャーがやるべきことだと思うようになりました。
それ以降は、その人の弱みと乗り越えてほしい課題は分けて考えることを意識するようにしてます。
メンバーの弱みと課題は分けて考えよう
相互理解を深めた「象、死んだ魚、嘔吐」

——では現職で、マネジメントで悩んだことはありましたか?
長くチームに在籍していたエンジニアが異動・育休で相次いでチームを離れることになり、チームの文化が途切れそうになった時ですね。
まだキャッチアップ中のメンバーもいる中で、ベテランたちから引き継ぎのバトンを渡されることになって、チーム全体が不安に包まれていました。
私はそのタイミングで前任のマネージャーからマネジメント業務を引き継いだので、何とかしなきゃと。
——そのピンチをどう乗り越えましたか?
チームに漂う不安の正体を突き止めること、お互いをよりよく理解することを目的に、外部のファシリテーターを招いてワークショップを実施しました。
「象、死んだ魚、嘔吐」という振り返り手法を試したのですが、これがとても効果的でしたね。
これは、普段言えないことや放っておくとまずそうな課題などを皆で吐き出す振り返り手法です。
自分たちの中にある不安、その中にある兆しなどを皆で理解し合って改善に向けて動いたことで、1カ月くらいでチームの雰囲気ががらっと変わりました。
Airbnbの共同創業者ジョー・ゲビアが提唱した手法。三つのテーマを設定し、メンバーそれぞれが思っていることをふせんに書き出して発表してもらう。
1.「象」は、口に出さないけれど全員が知っている課題
2.「死んだ魚」は、放置するとまずいことになる課題
3.「嘔吐」は、胸の内にある課題
その内容についてチームメンバーがお互いに質問し合い、内容の深掘りを繰り返していくことで、課題を洗い出していく。
皆で不安を吐き出して相互理解を深めよう
——良い取り組みですね! またエンジニア組織は「全員プロフェッショナル」のようなイメージもありますが、そのあたりでマネジメントの難しさはありますか?
おっしゃる通り、当社のエンジニア組織は皆スキルが高く尊敬できるメンバーばかり。ですがその分、つい頑張りすぎてしまう傾向もあるのもたしかです。
「いまお客さんが困っているから無理して差し込もう」とか、短期的な成果を求めすぎると息切れして続かなくなってしまうこともありますよね。
当社が大事にしている価値観のひとつに「中長期で成果を出せる働き方を」というものがあって、それは自分たちがやっている戦いはマラソンであり、今この瞬間走り抜ければ勝ちなのではなくて長く走り続けられるチームでいようということ。
そうやってチームが長く走り続けられるように、ちょうど良いペースを見つけられるようにサポートすることをマネージャーとして意識しています。
チームが長期的に成果を出せる「ちょうどいいペース」を考えよう
自分の中の「リーダーはこうあるべし」を捨てよう
——女性管理職の登用を進めている企業が増えていますが、中には「管理職になりたくない」と考える20代女性も少なくない印象です。もし若手が「リーダーに“なってしまった”」と悩んでいたら、何と声をかけてあげたいですか?
マネジメントに性差はないので、まずは早く「女性管理職」とくくられない社会になるといいなと思います。
そのうえで「リーダーになってしまった……」と思う人がいるなら、多分それは自分が思う「リーダーはこうあるべし」という像と、自分の現状とのギャップに戸惑っているだけだと思うんですよね。
でも実際は、周りの人も新人がすぐにリーダーとして振る舞えるようになるとは思っていません。
それを念頭に置いた上で、なぜ自分が期待されたのか、理想のためにどんな道筋を描いていけるのかを、素直に周りの人に聞いてみたらいいと思います。
意外と周りに聞かずに「リーダーを任されちゃったから頑張らなきゃ」とか「私には無理です」って人が多いようにも思うので、ぜひ自分の頭の中で完結せずに、周りの力を借りながら挑戦してみてほしいですね。
周りに自分への期待を尋ねてみよう
取材・文/大室倫子(編集部)







