口うるさくしなくても挑戦する子の親は何が違う? ビリギャル本人に聞いた「親子で一緒に」幸せになる方法【小林さやか】

仕事後の保育園ダッシュ、慌ただしい夕飯、お風呂、寝かしつけ……嵐のように過ぎる夜の時間。
そんな時間に追われる毎日に、「子どもとの時間が足りない」「ゆっくり向き合ってあげたいのに」と罪悪感を持つ母親は少なくないはず。
そんな切実な悩みに答えてくれたのは、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(KADOKAWA)の主人公、「ビリギャル本人」の小林さやかさんだ。
自身の劇的な経験に加え、昨年まで米国コロンビア大学大学院で認知科学を学ぶなど、「人が自己効力感を育み、挑戦し続ける方法」を探求してきた彼女。
限られたふれあい時間の中でも、子どもの自己肯定感をしっかりと育み、親自身も前向きに仕事に向き合うためのヒントを教えてもらった。
子どものために、まずは自分の幸せを追求しよう
私が働くママたちに一番伝えたいのは、「まず、ママ自身が自分の人生をしっかり楽しんで生きること」。これが、子育てにおいて何より大切な大前提だと思います。
なぜなら、子どもたちは驚くほど保護者のことを見ているから。
「ママやパパは、毎日どんな顔で、どんな言葉で、どう生きているか」を敏感に感じ取り、無意識のうちに自分の生き方のロールモデルにしているのです。
もし、親が何かを我慢しながら生きているとしたら。それはお子さんが将来、同じように我慢する姿を望んでいるからでしょうか? きっと違いますよね。
「子どもの幸せを願うなら、まず親である自分自身が、自分の人生を楽しんで幸せに生きること」。それが、お子さんの未来への最高のプレゼントになると断言できます。

私は講演などでお子さんに関する相談をよく受けるのですが、いつも感じるのは「子どもを変えたいなら、まず大人が変わらなければ」ということ。これは、私自身の経験からも強く感じています。
私が「ビリギャル」として知られるようになったきっかけは、自分を変えたくて中学受験をし、その後ギャルになり、恩師との出会いから慶應義塾大学を目指したことでした。
この経験をお話しすると、子どもたちは素直に聞いてくれるのですが、大人からは「さやかさんは特別だから」「もともと地頭が良かったんでしょ?」と言われてしまうことも少なくありません。
でも、「ビリギャル」の話で本当に大切なのは、「私だからできた」ではなく、「なぜがんばれたのか」というプロセスです。そこにたくさんのヒントがある。
そのメカニズムを解き明かしたくて、私は留学して認知科学を学び、『私はこうして勉強にハマった』(KADOKAWA)という本も書きました。
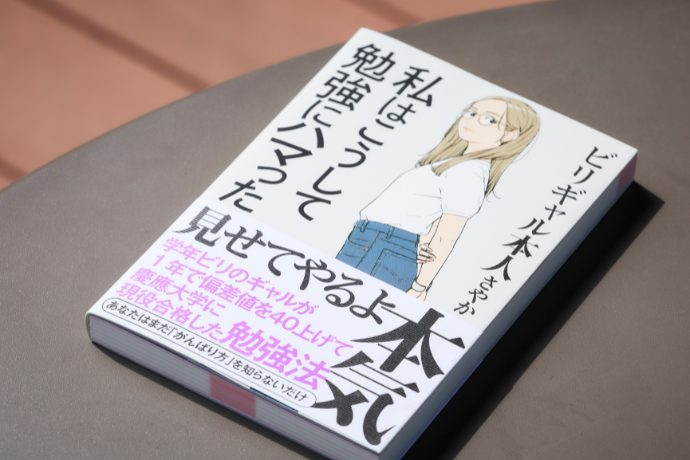
この「人は正しい動機づけと、成果がちゃんと出る努力の仕方を知ることができれば、誰でも変われる、がんばれる」という確信は、昨年起業して大人向けの英語学習プログラムを準備する中で、ますます強まっています。
英語に自信のなかったモニターの人たちが、みるみる自信をつけていく姿を目の当たりにして、「大人だって、何歳からでも変われるんだ!」「大人でもこんなにうれしそうに笑うんだ」と感動する毎日です。
特に変化が大きいのが、女性の参加者。大人になっても挑戦して自信をつければ、こんなに生き生き輝けるんだと改めて感じました。
しかし日本では、さまざまな役割の中で、無意識に我慢しながら生きている女性が少なくないように感じています。
もちろん、それが自分で選択したことならすばらしいと思いますが、そうじゃない人もまだまだ多い。
「自分がどう生きたいか」を考えたとき、無理のない範囲でいいから、もっと我慢せずに生きていいと思うんですよね。
「2種類の幸せ」を知れば、満たされ方が変わる
まずは親自身が幸せになることが大切。そう言われても、何をもって幸せと言えるのか、今以上に何をすればいいのか、戸惑う人もきっと多いですよね。
実は、「幸せ」には大きく分けて二つの種類があると言われています。
一つが「ヘドニック・ウェルビーイング」。これは、美味しいものを食べたり、欲しかったものが手に入ったり、物質的に恵まれていることで感じる「うれしい」「楽しい」といった、喜びや快楽からくる幸せです。
例えば、お金と時間がたくさんあって、ハワイのビーチでずっと寝転がってのんびり過ごす……最高の「幸せ」に思えますよね。でもそういう状況って、長く続くとだんだん当たり前になって、飽きてしまいます。
そこでもう一つの幸せのかたちが「ユーダイモニック・ウェルビーイング」。こちらは目標に向かって努力したり、困難を乗り越えた時の達成感、何かに夢中になって成長したりする中で感じる、持続的で深い充実感ややりがいからくる幸せのことです。
部活を頑張ったり、学園祭をみんなで成功させたりしたことがある人は、何となくピンとくるのではないでしょうか。

日本の働くママたちは衣食住に恵まれている人が多いので、「ヘドニック」な幸せの基盤は十分にあるでしょう。
なのになぜか人生に物足りなさや不安を感じるのは、「ユーダイモニック」が欠けているからです。
「ユーモダイニック・ウェルビーイング」を上げるには、「やってみたい」ことを見つけて、挑戦してみること。「私にもできた!」という小さな成功体験と自信を、コツコツと積み重ねていくしかありません。
そうすることで、日常の中に、揺るぎない幸福感を安定して感じられるようになっていくはずです。
「働くママの姿」こそ最高の教育になる

親自身が「ユーダイモニック・ウェルビーイング」を大切にし始めると、時間をかけて意図的にコミュニケーションを取らなくても、子どもは親の姿を見て感じ取れるようになります。
「ママは最近、何してるの?」「実は、今こんなことにチャレンジしててね……」
そんなふうに、自分の挑戦やそこから生まれる喜び、時には葛藤さえもオープンに話してみてください。それ自体が、子どもとの対等で豊かなコミュニケーションにつながります。
そのときに意識したいのは「私(I)」を主語にして伝える「アイ(I)メッセージ」です。
「あなた(You)はこうしなさい」という「Youメッセージ」ではなく、「私はこう思う」「私はこんな経験をしたよ」と、自分の気持ちや経験を率直に伝えること。
この「アイメッセージ」のキャッチボールをすると、お子さんからも「私もこんなことがあったよ」と話してくれて、親子の間に深い信頼関係を育みます。
信頼関係を築いて、ママが子どもの憧れのロールモデルになったら、もう勝ちですよ!
「あれをしなさい、こうしなさい」と口うるさく指示しなくても、自分からやってくれるようになりますから。
ママが自分の人生を楽しみ、挑戦する姿が子どもにとって自然な憧れとなり、「ママみたいになってみたい」「自分も何かやってみたい」という主体性を引き出す理想の関係につながっていくはずです。

そしてもう一つ、子どもの成長を見守る上で欠かせないのが、「結果だけでなくプロセスを見る」という視点。
私たちはつい、目に見える「結果」に一喜一憂しがちです。でもたとえ望む結果が得られなかったとしても、そこに至るまでの努力や工夫、経験したことすべてに、かけがえのない価値があります。
だからこそ親として、たとえ望んだ結果が得られなかったとしても「1年前よりもできるようになっているんだから、大成功じゃない?」と、結果がすべてではないというマインドセットを、日々の会話の中で伝えてあげてください。
この「プロセスを認める」関わり方は、お子さんが将来、困難にぶつかった時に自分の力で立ち上がり、再び前を向くための「心の土台」を育みます。
ほとんどの親は、子どもよりも先に死んじゃいますよね。でも「あの子は失敗して立ち直れるかな。大丈夫かな」なんて思っていたら、死んでも死に切れないじゃないですか!
「あの子は自分で乗り越えられるから大丈夫」と思えるようになるためにも、プロセスを見るマインドを育むことは大切なのです。
ママが自分の人生に目標を持ち、悩みながらも挑戦し、生き生きと輝いている姿。それ自体が、お子さんにとって最高の生きた教材であり、未来を生き抜く力を育む土壌となります。
関わる時間が少なくたって、子どもはちゃんと親を見ています。だから、働くママは子どもに対して罪悪感を感じる必要なんて全くありません。
「ママは今、こんなことに挑戦しているんだ」。どうかそのことを誇りを持って、お子さんに伝えてほしいです。
親が生き生き生きている姿を見せることこそが、子どもたちの可能性を広げる、最高の教育になるのですから。
取材・文/石本真樹 撮影/赤松洋太 編集/大室倫子(編集部)
書籍情報:『私はこうして勉強にハマった』(サンクチュアリ出版)
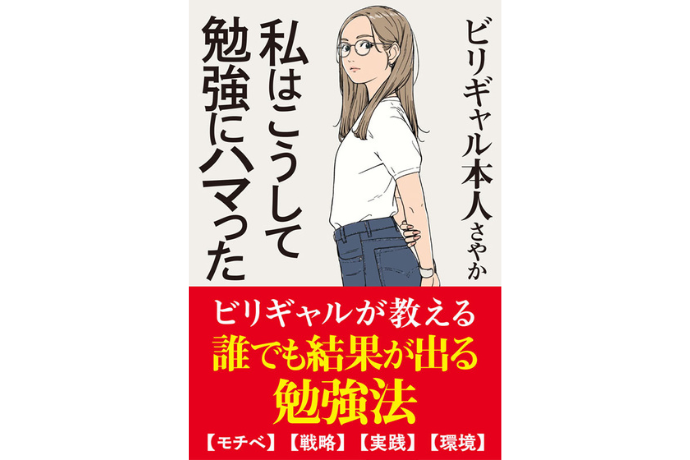
学年ビリから偏差値を40あげて慶應大学に現役合格した著者ビリギャル本人であるさやかが、コロンビア大学院で「認知科学」を研究した結果分かった「ビリギャルがなぜ頑張れたのか」を言語化。中学生でも読める「誰でも必ず伸びる最強の勉強方法」を公開。
勉強に自信が持てない。勉強をがんばっているけど、なかなか成果が出ない。そんな人たちにぜひ読んでほしい一冊です。






