【ヒューストン・バレエ最高位プリンシパル加治屋 百合子】20代で周囲との比較に苦しんだ彼女が「自分にしかない強み」を見つけるまで

この連載では、各界のプロとして活躍する著名人にフォーカス。 多くの人の心をつかみ、時代を動かす“一流の仕事”は、どんなこだわりによって生まれているのかに迫ります
アメリカのヒューストン・バレエで最高位プリンシパルを務める加治屋 百合子さん。
彼女が初めてアメリカに渡ったのは17歳の時。世界のトップダンサーが集うエンターテインメントの聖地に身を置き、しのぎを削り合う日々を20年以上にわたって過ごしてきた。

加治屋 百合子さん
愛知県出身。8歳でバレエを始め、10歳で上海舞踊学校入学、奨学金を得て首席で卒業。在学中の2000年、若手バレエダンサーの登竜門であるローザンヌ国際バレエ・ コンクールでローザンヌ賞を受賞。奨学金を得てカナダ国立バレエ学校入学。 翌年アメリカン・バレエ・シアター (ABT)スタジオカンパニー入団。 同バレエ団の研究生を経て正団員となり07年ソリストに昇格。14年ヒューストンバレエ団移籍後、最高位プリンシパルとして舞台を踏む■X
ただ、取材の場に姿を見せた彼女からは、勝ち負けへの執着もとげとげしさも一切感じられない。
「今日よりも明日、もっとうまく踊りたい。自分らしく舞台で輝きたい」
柔らかな笑顔を浮かべ、穏やかな口調で仕事に対する自身のスタンスを語る。
40代を迎えた今もなお成長し続けるトップバレリーナを突き動かしてきた原動力とは、一体何なのだろうか。
前回の来日公演は「不安」もあった

2025年7月、加治屋さんがプリンシパルを務めるヒューストン・バレエの来日公演(東京文化会館/愛知県芸術劇場)が幕を開ける。
同バレエ団の公演は、22年の初来日以来3年ぶり。特に注目されているのが、加治屋さんが主役を務める『ジゼル』だ。
同バレエ団の芸術監督で、今回上演する『ジゼル』の振付・演出を務めたスタントン・ウェルチ氏は、「この『ジゼル』は百合子にインスピレーションを受けて製作した。彼女のジゼルは、人生を通して見てきた中で、最高レベルのジゼル」だと加治屋さんの踊りを絶賛。

Houston Ballet Principals Yuriko Kajiya as Giselle and Connor Walsh as Albrecht in Stanton Welch’s Giselle.
Photo by Amitava Sarkar (2019), Courtesy of Houston Ballet.
『ジゼル』は古典的で深みのある作品ですが、今回上演するバージョンは伝統的な要素と現代的な感覚がバランスよく織り交ぜられた作品になっています。
テクニック面に注目していただきたいのはもちろんのこと、キャラクターの内面を豊かな感情表現で届けたいですね。
前回の来日公演では、『白鳥の湖』主役のオデット/オディールを務めた加治屋さん。
ヒューストン・バレエの公演を日本の観客がどのように受け止めるのか、公演が始まる前には「不安もあった」と当時の心境を明かす。

Hidemo Seto©Koransha
私自身はずっとアメリカにいるので「当たり前」になってしまっているのですが、ロシアなど他国のバレエと比較しても、アメリカのバレエは非常にエンターテインメント性が高いところが特徴です。
ですから、アメリカのバレエにあまりなじみのない日本の皆さんが私たちの公演をどう受け止めるのか、心配なところもありました。
ただ、実際に舞台が終わると「ブロードウェイ・ミュージカルのようなエンターテインメント性があって楽しかった」「これまでと違う『白鳥の湖』の面白さを知った」という声をたくさんいただき、ほっとしました。
日本の皆さんからいただいた感想によって、私自身もヒューストン・バレエならではの魅力を再確認させてもらえましたね。
2度目の来日公演に向けて、約1年前から技術面の課題をクリアするための練習を重ねている加治屋さん。
本番で「豊かな感情表現」に集中する余裕を生むために、じっくり時間をかけてテクニックを磨くーー。それが加治屋さんのスタイルだ。
テクニックを磨くほど、より広い視野で役を捉えることができるようになります。
いまは過去に踊った『ジゼル』の舞台映像を見返しながら、さらに改善できるように模索しているところです。

Houston Ballet Principals Yuriko Kajiya as Giselle and Connor Walsh as Albrecht in Stanton Welch’s Giselle. Photo by Amitava Sarkar (2019), Courtesy of Houston Ballet.
20代後半で学んだ、自分にしかない「強み」を磨く大切さ
10歳で中国に留学し、カナダ、アメリカと活躍の場を移してきた加治屋さん。バレエダンサーとしてのプロ意識は、上海留学中にたたきこまれた。

そこからキャリアを重ね、ソリストやプリンシパルを務める立場へと成長。自身のプロ意識も徐々に変化してきたという。
学生時代もプロ意識を持って踊っていましたが、バレエ団に入団した時点で、一人の大人として扱われ、さまざまな責任を負うことになります。
入団一日目でもプロに違いありませんが、だからといってそこがゴールではない。プロになってからが本当のスタートです。
常に自分自身に挑戦し続け、自分を磨き続けること。それが「プロとして仕事をする」ということなのだと考えるようになりました。
努力を「当たり前」に続けること。そして、努力するプロセスをも楽しむこと。
「向上心を持って努力し続けられる自分」を維持することは、言葉で言うほど簡単なことではありません。
だからこそ、それができる人を真のプロフェッショナルと呼ぶのではないでしょうか。
加治屋さんが目指すのは、過去の自分を乗り越えること。今日よりも明日、良い演技をすることを追い求めている。
だが、20代前半の頃は周囲のダンサーと自分を比較し、自信をなくすことも多かった。
アメリカン・バレエ・シアター(ABT)に入団したばかりの頃は、長身で手脚が長くバレエ特有の甲の高さを兼ね備えた欧米のダンサーたちに囲まれ、自分との体格差に衝撃を受けた。
同じ時期に入団したダンサーたちは、次々と主要なポジションを得てキャリアアップしていくーー。そんな中で、くすぶっている自分に焦ることもあった。

人間なので、どうしても他人と比べてしまうことはあると思います。
でも、これは子どもたちにバレエを教える時にもよく言うのですが、「自分という人間は世界に一人しかいない」んですよね。
似ている人はいるかもしれませんが、自分はやっぱり自分だけ。つまり、自分にしかない良さや強みを、誰しもが持っているんです。
テクニック面などで克服すべき課題には取り組みつつ、自分の良いところ、舞台に立った時に武器になる部分を磨いていくこと。これが何より大事です。
周囲との比較ではなく、自分だけの良さを探すーー。そんなふうに視点を変えられるようになったのは、20代半ばを過ぎてアメリカン・バレエ・シアター(ABT)でソリストになったことがきっかけだった。
ないものねだりをしていても仕方ない。アジア人だからこその表現力や強みが必ずあるはず。
そう気付いてからは、「自分にしかないもの」を武器にしていこうと考えられるようになりました。
例えば、コール・ド・バレエ(群舞)では、みんなで同じ衣装を着て、同じ髪飾りをつけ、同じ振付を踊ります。
20人ほどのダンサーが一人のように、完璧にそろって踊ることが求められるのです。そんな中でも、「どうすれば大人数の中でも輝けるだろうか?」と常に考えていました。

他のバレエ団の公演を観ても、同じコール・ド・バレエの中で、なぜか目を引くダンサーがいるんです。
それは単に足が高く上がるとか、技術的に優れているということだけではなく、その人だけが持つオーラのようなもの。
一つのポーズで長く静止するような場面でも、ただ止まっているのではなく、内側からエネルギーを放ち続けること。
指先まで意識を張りめぐらせて、より長く美しく見せること。そういった見えない部分での努力を、誰かが見てくれていると信じて、常に意識してきました。
そうすることできっと、舞台上で「輝くもの」があるはずですから。
キャリアのゴールは人それぞれ違っていい

Hidemo Seto©Koransha
とはいえ、加治屋さんが身を置くのは世界各地から集まったトップレベルのダンサーたちが「競い合う」ことが当たり前の世界。
そんな中で、周囲と自分の力量や評価を比較しては悩む……そんな負のスパイラルを抜けられるようになったのには、もう一つのきっかけがあった。
20代から30代へ、年齢とキャリアを重ねるにつれて、「皆が同じゴールを目指しているわけではない」ということに気が付きました。
バレエ学校時代は、皆が『白鳥の湖』のオデット/オディールや『ロミオとジュリエット』のジュリエットを踊りたいから努力しているのだと思っていたんです。
でも、バレエ団に入り、最初は一番下のコール・ド・バレエから始まりますが、そこには同世代もいれば10歳以上年上のダンサーもいて、全員がプリンシパルを目指しているわけではない。
当たり前ですが、そういう現実に気づいたんです。
コール・ド・バレエで輝くことを目標とする人、結婚や出産までバレエを続けたいと考える人……人それぞれ違うゴールがあっていい。
そう考えられるようになった途端、よりいっそう「自分らしい踊り」を意識できるようになった。

Hidemo Seto©Koransha
さらに、30代に差しかかる頃に気づいたのは、「人それぞれ開花する時期が違う」ということです。
お花と一緒ですね。それがその人の人生でありキャリアなのだから、それでいいのだと。
20代前半は自分のことで精いっぱいで、周りが見えていなかったので、精神的に苦しんだ時もありました。
その時期も無駄ではなかったけれど、今なら「ウサギとカメ」の話のように、人にはそれぞれの道があり、ペースがあるということが分かります。
役が早くつく人もいれば、時間がかかる人もいる。それはその人の歩む過程であって、早ければ良いというものでもない。
自分のペースで進んでいけばいいのだと気づかされてからは、周囲に惑わされることが一気に減ったように思います。
ただ、20代の頃に焦りを感じていたからこそ、「努力する意欲も湧いた」と加治屋さんは言う。
振り返ればつらいこともたくさん経験した時期でしたが、そういった葛藤や苦労を経験することは、とても大切。
中国の言葉に「苦さを知っているからこそ、甘いものの本当のおいしさが分かる」というような意味合いのことわざがあります。
20代の頃は思い切り悩んでいいし、苦労してもいい。それを抜けた先で得られる喜びや達成感が、より価値のあるものに感じられるはずですから。
自分に挑戦し続けることが、モチベーションを向上させる
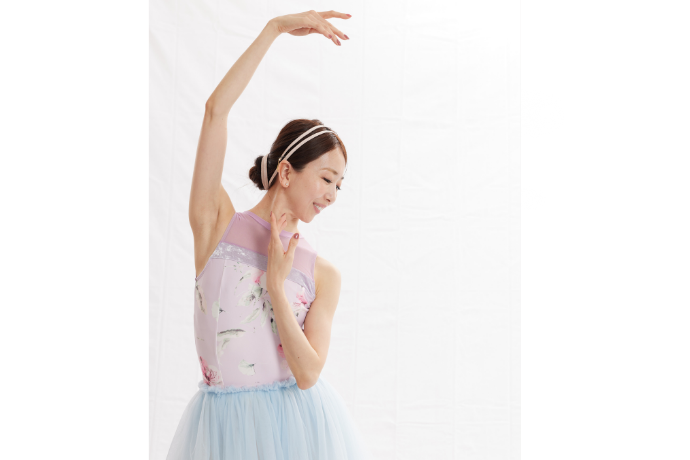
Hidemo Seto©Koransha
40歳になった今、加治屋さんは「常に上を目指して、より良いものを追求し続けたい」と意気込みを語る。
バレエの世界で長く挑戦を続けてきた加治屋さんがプロのダンサーとしてこだわるのは、ステップとステップの間にある「つなぎ」の部分だ。
ダンサーとして一つ一つのステップをこなすことは、練習を重ねれば多くの方ができるようになるかもしれません。
ただ、そのステップをいかに自然に、滑らかにつなげていくか。踊り全体を見たときに、ギクシャクせず、余裕があるように見えるか。
一つ一つの動きに説得力を持たせるためには、その「つなぎ目」をどうスムーズに見せるかが非常に重要で、私自身はそこに一番の重点を置いて練習しています。
次回の来日公演の『ジゼル』しかり、バレエの世界では同じ役を演じることが多い。
そんな中で常にモチベーションを保ち続けるためには「自分自身への挑戦をやめないこと」が何より大切なのだと加治屋さんは言う。
舞台に立つバレリーナは優雅に見えるかもしれませんが、その裏には膨大な努力と、舞台に立っている時間の何十倍、何百倍ものリハーサル時間があります。
役に取り組み、舞台に立つまでの過程で自分自身を成長させる。その挑戦を続けること、そしてそのプロセス自体を楽しむこと。
それができなければ、これほど厳しい世界に身を置き続けることはできないと思います。
加治屋さんの根底には、バレエに対する強い愛がある。そして、彼女を挑戦に向かわせる最も大きな原動力となっているのが、声援を送り支えてくれる人たちの存在だ。

何より勇気づけられるのが、お客さまの存在です。「自分のため」だけでは、ここまで頑張り続けることは絶対にできませんでした。
皆さんが期待を寄せて支え続けてくれるからこそ、バレエに向き合うことを諦めずにいられます。
7月の公演でも、皆さんに非日常を過ごす喜びや感動を届けたい。そして、バレエの魅力を一人でも多くの人に味わってもらえる時間を提供できたらと思います。
来日公演の開幕を、ぜひ楽しみにしていてくださいね。
公演情報
全米屈指の実力を誇り、2022年の初来日公演で鮮烈な印象を残したヒューストン・バレエが待望の再来日<2025年7月東京・名古屋にて開催>
HP:https://www.koransha.com/ballet/houston/
取材・文/栗原千明(編集部) 写真提供/加治屋 百合子さん
『プロフェッショナルのTheory』の過去記事一覧はこちら
>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/rolemodel/professional/をクリック







