「相手を喜ばせたい」と思えない人もいる? 接客業を続けた人・辞めた人が明かす、向いている人が共通して持つ力
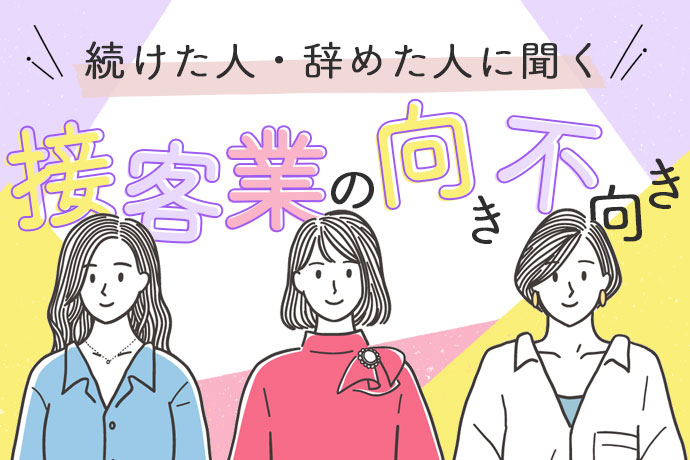
「お客さまに喜んでもらえる接客の仕事は好きだけれど、実績がついてこない……」
「自分に接客業は向いていない気がする」
そんな悩みを持ちながらも、日々顧客と向き合っている女性も多いかもしれない。
そこで、接客業を続けた人・辞めた人の双方にインタビューを行い、「接客業の適性」について探ってみた。
今回話を聞いたのは、こちらの3名。
【1】小川裕子さん(仮名):携帯電話ショップ販売員歴22年の店長
【2】森本加奈さん(仮名):飲食店→セラピストと業界を変えて接客の仕事を続けているリラクゼーション店店長
【3】大木美穂さん(仮名):接客業→人事へとキャリアチェンジした、元アパレル販売員
「今だからこそ、自分が向いていたかどうかが分かる」と話す3人の話を聞くと、向いている人たちが共通して持つ「ある力」が浮かび上がってきた。
携帯電話ショップ販売員歴22年「接客の楽しさを知るきっかけは、不機嫌なお客さまだった」

小川裕子さん(仮名)
2001年、携帯電話ショップに新卒入社。販売員歴22年。産休・育休をへて、現在は店長としてスタッフマネジメントを担う
小川さんが携帯電話ショップに新卒入社したのは、今から22年前。接客業がやりたかったわけではなく、「当時人気だった」という理由で選んだ仕事だという。
始めたばかりの頃は、携帯電話に関する知識も接客スキルもなく、来店客から叱られることが多かった小川さん。
「楽しくない、この仕事は私に合わない」毎日のようにそんな思いを抱えながら働いていた。
でもこの時は、自分のスキルが足りていないせいだとは思ってなくて。
「お客さまが分かってくれない」と他責にしていたので、お客さまへの不満が表情や態度に出てしまっていたのかもしれません。
結果、お客さまから信用を得られず、なかなか接客の仕事を楽しめるようにならなかったのだと思います。
「向いてないけど、まあいいか」。もともと長く働き続けるつもりではなかった小川さんは、そんな気持ちで何となく続けていた。
そんな彼女に変化が現れ始めたのは、入社から3~4年ほどたった頃。
専門知識も付いてきて、来店客からの質問にもスムーズに答えられるようになり、顧客との関係性が変わってきたという。
「あなたに担当してもらえてよかった」「次来る時もお店にいてね」と私宛に来てくれるお客さまが増えてきて。
会社の広報誌に、私に宛てられたお客さまのアンケートが載ることもあり、少しずつお客さまからの「ありがとう」がやりがいに変わっていきました。
接客スキルが上がるにつれて、小川さんを指名する予約が絶え間なく入り、そんな期待に応えたいと思う。これを繰り返していくうちに、気付けば入社時に想定していたよりもずっと長く働き続けていた。
産休育休をへて、現在は店長としてスタッフのマネジメントをメインに担っている小川さん。入社から22年たった今、「接客業は天職だった」と笑顔を見せる。
お客さまから「ありがとう」と言ってもらえること。誰かの役に立てている実感を得られること。お客さまの喜んでいる顔を見られること。
これらすべてがやりがいにつながっています。今は接客業をやっていて良かったと、心から思います。
22年にわたり、成長する人、早く辞めてしまう人、あらゆる人たちを見てきた小川さん。
そんな中で、向いている人にはある共通点があると話す。
「お客さまに矢印が向く→お客さまが求めているサービスを提供できる→感謝される→自分がうれしい」このサイクルがモチベーションになる人は、接客業に向いていると思います。
逆に、向いていない人はベクトルが最初から自分に向いている。つまり、自分の利益や感情が先に立つ傾向があります。
常に顧客にベクトルが向いていると、ちょっとした機微を敏感に察知できるため、「かゆいところに手が届く」接客ができると、小川さんは分析する。
はたから見ていて「あのお客さま、不満そうな顔してるよ」と思っても、ベクトルが自分に向いているとそれに気付かないんですよね。そのまま応対を続けてしまうとお客さまの不満がつのり、コミュニケーションがギスギスしてしまう。
結果、「あんなお客さまばかり来て嫌だ」と不満につながり、それが表情に出てしまい、次の接客もうまくいかない……という悪循環に。そうすると接客がつらくなっちゃうんです。
とはいえ、小川さんも入社当時は自分にベクトルが向いていて、接客がつらかったと話していた。顧客の方を向けるようになったきっかけは「故障担当」に10年配属されたことが大きい。
故障担当が対峙するお客さまは、出だしから不機嫌なことが多いんですよね。
最初はどんな風にモチベーションを保っていいのか戸惑うこともあったのですが、「最初は不機嫌だったお客さまをいかに笑顔で帰せるか」に心を燃やすようになると、それまでは得られなかったやりがいを感じられるようになっていったんです。
顧客が何に怒っているのか、何を解消すればいいのかを察知して対応し、最終的に「来て良かったよ」「不安が解消したよ」と言ってもらえる喜びを知った小川さん。
故障担当をへて「顧客の気持ちを変化させる」ことにモチベーションを置けるようになったこと。これこそが、接客業を天職にする第一歩となったようだ。
飲食店→セラピスト「“相手に興味を持つ”ことで、マッサージ日本一に」

森本加奈さん(仮名)
新卒で大手飲食チェーン店に入社。1年半ほど働いた後退職。その後、セラピストを目指しバリに留学。帰国後は大手のスパに転職。のちに独立し、現在は都内でサロンを2店舗経営する傍ら、現役セラピストとして施術も行う
学生時代に飲食店でアルバイトをしていた経験から、接客の仕事に楽しさを見いだし、飲食店に就職した森本さん。
希望通りの仕事に就いたものの、就職先が回転の速いチェーン店だったこともあり、来店客一人一人と関係性を築いていくことができない環境に、はがゆさを感じるようになっていった。
キッチンから出られないことも多かったですし、お客さまと深い話ができる環境ではなくて。
学生時代は田舎のゆったりしたレストランでアルバイトをしていたので、常連さんと関係性が築けて楽しかった分、「さみしいな」と思うようになっていったんですよね。
そんな彼女が次の道として選んだのは、顧客に寄り添いながら癒やしを与えられるセラピストの道だった。
バリに留学し、セラピストとしての基礎を身に付けた森本さんは帰国後、大手のスパに転職。現在は都内にサロンを立ち上げ、経営する傍ら現役セラピストとして施術も行っている。
飲食業とセラピスト。毛色の違う仕事ではあるけれど、飲食店で培った「顧客が求めていることを察する力」は今も生かせているという。
例えば、キョロキョロしているお客さまを見て「あの人は何を求めているのかな」と察したり、水がなくなる前に注いだりと、飲食店では常に視野を広げて先回りしたサービスを提供する必要があります。
こういったものは、セラピストの世界でも共通して生かせる力。施術中に「ちょっと鼻が詰まってるな」と思ったらティッシュを持ってくるとか、ちょっとした気遣いがお客さまの満足度を大きく変えるんですよね。
これを自然とできるのは、飲食業の経験があったからこそだと思います。
二つの接客業を経験した森本さんは、どちらの仕事においても、向いている人は“共通する特徴”を持っていると話す。
「他人に興味を持てる人」には、どちらの仕事も向いていると思います。
先ほど話したような、「お客さまが求めていることを察する」のも、相手に興味がなければ難しいですよね。
これまでに辞めていってしまった人たちを見ると、お客さまに興味を持てなかった人が多いように思います。
相手に興味を持てないから何を話していいのか分からないし、会話が盛り上がらずお客さまと距離を縮められない。だからお客さまとの時間を楽しめないのだと思います。
だが、セラピストのような技術を伴う接客業の場合、「接客は苦手だけれど、技術で突き抜けている人」も向いていると言えるのではないか。
そんな疑問に対し、「技術で突き抜けるには時間がかかる。その技術が身に付くまでを補うのが接客力」と森本さん。
そして、相手に関心を持つことは、技術力を高めることにもつながると続ける。
お客さま一人一人の異なるご要望に応えていくと必然的に技術の幅も広がりますし、お客さまの反応を見ながらベストな施術を学んでいける。
結果として、技術力そのものも上がっていくんです
そんな森本さんは先日、マッサージの日本大会において、見事優勝を収めた。大会の評価基準には技術だけでなくおもてなしの要素も含まれ、「相手を喜ばせたい気持ちが伝わってきた」ことも評価されたポイントの一つだったと笑顔を見せる。
おもてなしの心があれば技術力は高まり、技術力が高まればより良いおもてなしができ、お客さまからはより良い反応が得られる。
それがモチベーションとなり、接客力と技術力をさらに高める好循環が生まれるのだと思います。
アパレル販売→人事「“お客さまのうれしい”を喜べるなら、見切りをつけるのは早いかも」

大木美穂さん(仮名)
新卒でアパレル企業に入社。4年半ほど販売員として働いた後、自らの希望で人事へと異動。現在は中途採用・アルバイト採用を担当
就活時にこれといった軸がなかったという大木さん。一緒に働く人が決め手となってアパレル販売職に就いた。
しかし、もともと接客・販売の仕事を強く希望していたわけではなかったこともあり、最初は「向いてない」と思うことも多々あったと振り返る。
アパレル販売の現場では、一度に販売する服の点数やリピーターの人数、自分に会いに来てくれるお客さまがいらっしゃるか……そういったところにスキルが表れます。
私は社員でしたが、アルバイトの方でも私よりスキルが高い人はたくさんいたし、そういう人たちの上に立って働くことに難しさを感じることはよくありました。
そう思いながらも「接客の仕事自体は好きだったから4年半続けられた」と語る大木さん。
5年目を迎えた時、「もっといろいろなことにチャレンジしたい」と人事部への異動を希望した。
もともと一生の仕事にしようと思って接客業に就いたわけではなかったし、自分らしく成長していくためには、一つのことをずっと突きつめるより、さまざまな分野で経験を積んで、スキルの幅を広げていきたいと思ったんです。
現在は人事としてアパレル販売員の採用に関わっている大木さんに、販売員の目線も採用担当としての目線も持ち合わせているからこそ見える、接客業の適性について聞いてみた。
「お客さまが喜んでくれること」を追求するのが接客業の面白さ。だから、常にお客さまに目が向いていて、お客さまを起点に動ける人は適性があると思います。
お客さま一人一人とじっくり向き合うことでお客さまが自分のファンになってくれる喜びだったり、メンバー皆でお客さまに愛されるお店を作り上げていく一体感だったり。
そこに楽しみを見いだして、周囲をよく見て相手の立場を考えながら柔軟に対応できる人は向いているんじゃないかな。
もし今、自身の適性に悩み、キャリアチェンジを考えている人がいるなら、まずは「少しでも楽しい瞬間があるかどうか」、そしてそれは「顧客が喜んでくれる瞬間かどうか」を振り返ってみるといいのでは、と大木さんは続ける。
お客さまが喜んでくれることに自分も喜びを感じるのであれば、「向いていない」と見切るのはまだ早いかも。
その気持ちを持ってお客さまと向き合っていれば、自然とファンが付いてきたり、感謝の言葉をいただけたりする機会も増えていくんじゃないかなと思います。
結果として違う道に進むことになったとしても、「接客業で得られる力には汎用性がある」と大木さん。実際に接客業で培った経験は、人事の仕事でも生きているという。
仕事をする以上、必ず人と関わりますよね。だからこそ接客業で得た対人スキルや臨機応変な対応力は、どんな仕事でも生かせるものだと思うんです。
人事の仕事でも、スケジュール通りに進まない時でも臨機応変に対応できたり、求職者の悩みや気持ちをくみ取ってコミュニケーションを取ったりできるのは、接客経験があってこそだと感じています。
一つの分野の接客業を追求した女性、転職をへて接客業を続けている女性、接客業以外の仕事にキャリアチェンジした女性。
三者三様のキャリアを築きつつも、接客業にやりがいを見いだしている彼女たちに共通しているのは、モチベーションの源泉が「自分」ではなく「相手の喜び」にあること。
「接客業なんだからそんなの当たり前」と思う人もいるかもしれない。
しかし、相手を喜ばせることにモチベーションを見いだせない人もいるということが、3人の話からは見えてきた。
顧客の「うれしい」を心から喜べるのは、決して当たり前じゃない。そう考えれば、その気持ちがある時点で「接客業に向いている」と言えるのではないだろうか。
顧客満足を追求し、人の心を動かせる力は専門スキルであり、それはきっと「長く働く」をかなえる大きな武器になるはず。
そして、その武器を身に付けるベースとなるのが「顧客が喜んでくれることに自分も喜びを感じる」性質だ。「相手のために」を突き詰められることこそが、接客業に向いている何よりの証なのかもしれない。
取材・文/光谷麻里(編集部)






