「こうあるべき」を求められる世の中で、自分らしく生きるための“疑う力”/『アートとフェミニズムは誰のもの?』村上由鶴
生き方も、働き方も、多様な選択肢が広がる時代。何でも自由に選べるってすてきだけど、自分らしい選択はどうすればできるもの? 働く女性たちが「私らしい未来」を見つけるまでのストーリーをお届けします
自分らしさが大事。
そう言われるけれど、同時に「女性らしく」「20代らしく」「会社員らしく」など、場所や場面によってさまざまな「〇〇らしさ」を求められる。
結果、根本にあるはずの自分らしさが分からなくなってしまう人も少なくない。
そんな中で、どうすれば自分らしく生きられるのか。アートと人権を軸に大学教員や執筆活動を行う村上由鶴さんに「自分らしさ」を聞いていくと、そのヒントが見えてきた。

村上由鶴さん
1991年、埼玉県出身。日本大学藝術学部写真学科助手をへて東京工業大学環境・社会理工学院社会・人間科学コース博士後期課程在籍。日本写真芸術専門学校非常勤講師。公益財団法人東京都人権啓発センター非常勤専門員。24年4月より秋田公立美術大学助教。写真やアート、ファッションイメージに関する執筆や展覧会の企画を行う。専門は写真の美学。著書に『アートとフェミニズムは誰のもの?』( 光文社新書) X / Instagram /webサイト
撮る、撮られると、人権の問題
私は写真を中心とした現代アートと、フェミニズムをはじめとした人権の分野を専門に活動をしています。
高校生の頃は雑誌が好きで。「雑誌の写真ページを作りたい」と思ったことから写真学科へ進み、勉強するうちに写真を使った現代アートに関心を持つようになりました。
人権について考えるようになったのも、写真がきっかけです。
写真を撮る、撮られることは、人権問題と関連します。例えばリベンジポルノは、撮ること自体が暴力であり、人権侵害になりますよね。
私自身、大学時代にアルバイトをしていたカメラ屋で違和感を持ったことがあって。社員さんから「女性のお客さんから証明写真の依頼があったら、プレミアムをおすすめしてね」と言われたことがあったんです。
プレミアムは、肌がツルッとして、目がはっきりする写真のプラン。「きれいに映りますよ」と女性のお客さんだけに勧めなければならないことに、疑問を感じていました。

その後修士課程に進み、就活をしたことで再び大きな違和感を抱いて。
面接官の男性から「君は言いたいことをはっきり言うタイプ?」と聞かれ、「間違っていると思ったことは言う方かもしれません」と答えたら、「そういう女の子はいらないんだよね」と言われたんです。
もうがくぜんとしてしまい、頭の中は真っ白。変だと思っているのに何も言えず、怒ることもできずにいました。
そんな自分に疑問を持ち、ジェンダーに関する本を読んでいくうちに、広い意味での人権問題へと関心が広がっていったように思います。
「自分らしく生きる権利」は与えられるものではない
今の私は「自分らしく生きられている」というほど確立はしていないけれど、少なくとも自分らしさを妨げられていない状態にはあります。
自分らしい状態をかなえるのに最低限必要なのは、「こうありなさい」という押し付けをされない状態。
というのも、自分らしさはすでにあるもの。だから「自分らしくなろう」というのは、そもそもちょっと違う気がしていて。

もちろん人との関係性や組織の中で、「この会社の社員らしく」など、自分以外のらしさを求められることはある。でも、そこにガチっとハマろうとしなくていいと思うんです。「自分のまま、この会社の社員らしくある」ことだってできるはず。
そう思う一方で、日本に暮らしている人は社会のルールとしての「こうあるべき」「こういうものである」から外れた人を見慣れていなさすぎるとも思っていて。だから型にハマろうとしてしまうんですよね。
本来は誰もが自分らしく生きる権利があるのに、どこかで「権利は与えられるもの」という感覚を持ってしまっているように思います。
例えば障害のある人が「こういう生き方がしたい」「こういうことに困っているからここを変えてほしい」といった主張をしたときに「えらそう」「わがまま」みたいな批判が起きてしまうのも、「権利を与えてもらいたいなら、えらそうにするな」という発想が社会にあるからですよね。
これは、自分が権利を持っている意識がないからこそ、権利を主張した人がズルしているようにも見えてしまっている状態です。それもあって、みんなと同じ権利を求める人に集中砲火があびせられてしまうのかなと思います。
特に女性や障害を持つ人など、マイノリティー属性に求められる「こうあるべき」ふるまいの中に「権利を主張する」「意見を言う」は含まれていないのでしょうね。

そもそも日本は「自分には権利がある」という意識が希薄な傾向にあります。
冗談めかして「社畜」という言葉が普通に使われているのも、本来は結構やばいと思うんです。「会社員だから間違っていると思うことでも従わなければいけない」「しょうがないことだ」みたいなマインドを多くの人が持っている。
実は、日本には人権を守る機能が整っていないんですよ。
基本的には各国に行政から独立した第三者としての人権機関が必要とされているのですが、日本の人権団体は国や自治体に付随しています。
つまり行政が人権侵害をしたときに、第三者が介入できる仕組みがないんです。
国連からは改善するよう指摘され続けていますが、そうした国のシステムもまた、日本の人権意識の低さにつながってるのではと思います。
自分らしさをかなえるのは「疑う力」
私たちはそんな社会で生きているから、自分の権利が侵害される状態にあっても、それに気付けない、おかしいと思えないことが多いのかもしれません。
自分の20代を振り返っても、「職場の花としての若い女の子」の役割を求められる場面で、ニコニコ振る舞っていたこともあります。
そういう圧がまだまだ強いからこそ、自分らしくいられる状態をかなえるには、試行錯誤が必要です。
大切なのは、「疑う力」を持つこと。ドラマの主人公のように声を上げて戦えない人でも、「変かも?」と疑うことから始めてみることはできるはず。
正直、日本の変化のスピードはとても遅いです。急にガラッと変わることはなく、かなりの長期戦になるでしょう。
でも、自分らしさが妨げられていることに気付き、試行錯誤する人が増えれば、社会全体へのインパクトにつながるかもしれません。

当たり前に受け止めていることを疑うのは難しいけれど、そのきっかけとしておすすめしたいのが、アートです。
例えば、フェミニズムの視点でアート作品を読み解くことは、自身の現状や社会的な思い込みを疑うきっかけになります。そんな提案がしたくて、『アートとフェミニズムは誰のもの?』を書きました。
アート以外にも、ドラマや映画、本など、自分の楽しめるエンタメ作品にも、「あれ?」と気付く意外なヒントがあるはずです。
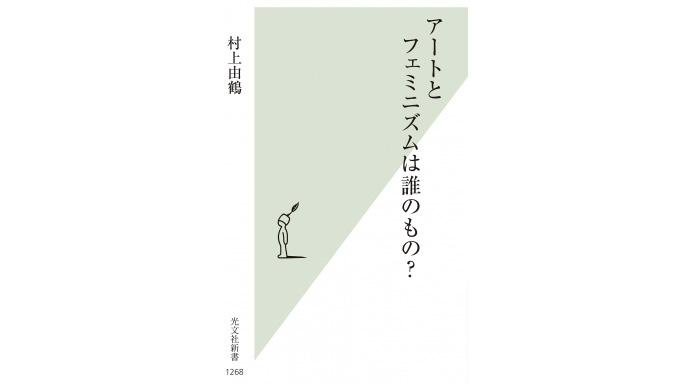
そうやって違和感に気づいたら、例えばムッとした顔で黙る、くらいの振る舞いはしてもいいんじゃないかなと思います。
おそらく日本で暮らす多くの人が、権利を主張する人を見慣れていません。
映画作品でも、差別的なことが起きた場面で、差別される側の人が黙って耐えるパターンが多く、「ふざけんな!」と文句を言ったり暴れたりして反逆する作品は少ないように感じていて。
残念ながら、女性が意見を言うことを良く思わない人もまだまだいる。それであれば、「どうしたの?」と突っ込まれ待ちをすることで言いやすい空気をつくるのも一つの工夫だと思います。
人生に対する貧乏性が、自分の道をつくった
今の私が自分以外の何かになろうとせずにいられて、かつ自分のアイデアや発言が尊重される環境を選べているのは、人生に対して貧乏性だったからかなと思います。
振り返ると「これをやったら次に役立つ」と思いながら人生の選択をしたわけではないけれど、自分で選んできたからこそ、「無駄にできない」という感覚が大きいんです。
この春から秋田公立美術大学の助教を務めるようになったのも、「社会の諸問題に関連する複合的な芸術表現の専門家を募集します」という公募に対し、「これなら過去に自分がやってきたことを回収できるな」と思ったから。
非常勤専門員として仕事をしていた東京都人権啓発センターの求人に応募した動機の一つも、応募資格の学芸員資格を持っていたからです。人権は関心領域でしたけど、せっかくなら資格を生かしたい気持ちも大きかったですね。
そうやって後ろをちょっとずつ振り返りながら、自ら人生の伏線回収をしようと歩んできました。
自分の過去を回収しようとすると、道を自分でつくっていくことになるじゃないですか。それはまぎれもなく自分の道でしかないんですよね。
だから今の私が自分らしさを妨げられない環境にいられているのは、貧乏性だからってことになります。「回収するぞ!」と意気込んでいるわけではなく、「もったいない!」みたいな感じ(笑)

今は美大の教員をやっていますが、アート、ジェンダー、写真、広告、メディアなどの分野を教養として、幅広く教える仕事がしたいと思っています。
アートってよく分からないじゃないですか。私自身そう思っていたし、理解するために美術批評を読んで分かるようになってきましたけど、美術批評って難解なんです。
普段使われない言葉で語られることも多く、「これってこういうことだよね?」と、かみ砕いた言い換えができる事柄も、そうは書かれていません。
それなら、その役割は自分が担えるかもしれない。
だから無理せず、気取らずに、アートやフェミニズム、人権に関して、自分のためにもかみ砕いて伝えたいんです。
そのためにはそのニュアンスを間違えないように拾うこともとても大事になるので、そこは特に気をつけています。
何より、「よく分からない」という顔をしながら美術館でさーっと歩いていってしまう人を見ると悲しくなってしまうのも大きいです。
私もかつて「意味分かんないな」と足早に通り過ぎたこともあるけれど、本当はアートって面白いんです。繰り返しになるけれど、アートを通じて疑う力を身に付けることもできますし。
せっかくなら楽しんでもらいたいから、アートの見方や楽しみ方を分かりやすく伝えることで、人々のアートへの理解を深めたい。
かつてのアートがさっぱり分からなかった自分を大切に保存しながら、アートになじみがない人たちとアートの世界との架け橋になりたいと思っています。
取材・文・編集/天野夏海 撮影/光谷麻里(編集部)
『「私の未来」の見つけ方』の過去記事一覧はこちら
>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/rolemodel/mirai/をクリック







