職場での男女格差、女性に偏るキャリア断絶…ジェンダーギャップのある社会で自分を守るヒント5選

少子化を防ぐためには「30歳過ぎたら子宮摘出」「女性は18歳から大学に行かせない」といった政治家の発言が物議をかもしたり、著名な芸能人による性加害への寛容さが問題視されたりと、昨今「女性の人権」について考えさせられるニュースが相次いでいる。
自分の身近なところに目を向けてみても、同じ仕事をしているのに男性の方が給与が高かったり、昇進スピードが速かったりと、ジェンダーギャップの大きさを感じることもあるかもしれない。
では、このような社会で女性が自分らしく働きながら生きるためには、どうすればいいのだろう。5人のインタビューからヒントを探ってみよう。
「産む・産まないを選択する権利」が脅かされないために/なんでないのプロジェクト・福田和子さん

日本でのSRHR(自分の性や体に関するあらゆることを自分で決め、守ることができる権利)実現を目指した活動を行う、福田和子さん。
「子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むか」を決める自由を持つこと。それに必要なヘルスケア・サービスを利用できること。これらは「権利」であると1994年の国際会議で決まったのに、30年たった今なお、日本には前時代の価値観が根付いていると話します。
今は「子どもが少ないから産んでね」と言われているけど、もし子どもの数が多かったら「産まないでくれ」って言われるんですか? という話ですよね。
そういう矛盾に気付かせてもらえないまま、「女性も働きましょう。ただし、子どもは産んでください」と言われる日本社会が生きづらいのは当然だと思います。
そんな社会を変えるためには、どうしたらいいのか。
福田さんの回答は、私たちでもすぐにできる“小さな一歩”でした。
“言葉の逆風”にキャリアを阻まれないために/東京大学准教授・中野円佳さん
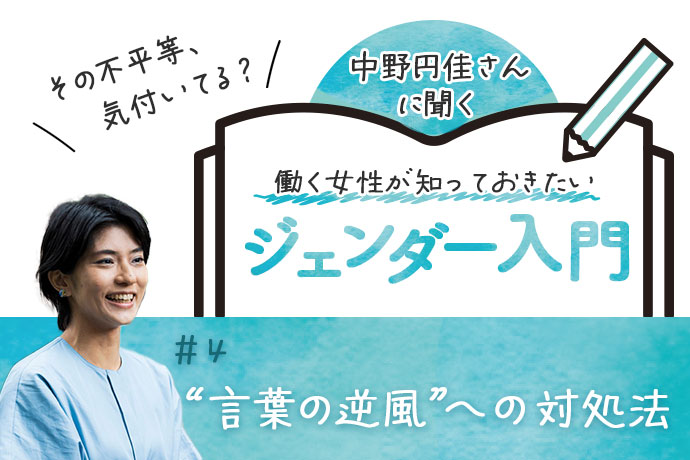
「女の子なんだから、地元の大学でいいでしょ」
「学歴つけても結婚できないよ」
これらの言葉は、実際に東大の女性たちがかけられてきたものだと話すのは、東京大学の准教授であり、ジェンダー問題の若き論客である中野円佳さん。
学生時代に限らず、あらゆる女性に対して、仕事でリーダーシップを取ることや、実力を発揮すること、政治に参画すること、声を上げることについて、意欲をくじいたり、進みたい道に進もうとすることを阻んだりする“言葉の逆風”が残念ながらまだあります。
働き始めてからも吹き続ける逆風ですが、とりわけ結婚・出産をへてから強く吹くそう。
では、そんな社会で女性たちはどのように生きればいいのでしょうか。
「DV加害者に甘い国」で自分の身を守るために/公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さん
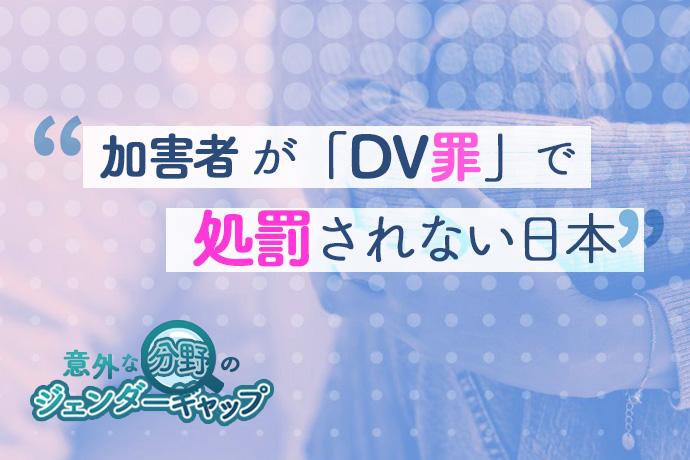
「DV防止法の柱は被害者保護と予防の二つ。実は、加害者への罰則はないのです」
そう語るのは、長きにわたりDV問題に向き合ってきた公認心理師・臨床心理士の信田さよ子さん。
法学部の先生に聞いたのですが、日本の法律では、家族内で起きたことを犯罪化し、その加害者を処罰することは難しいのだそうです。
DVで妻が怪我をしたら傷害罪、親からの虐待で子どもが死んだら殺人罪に問われますが、DV罪や虐待罪ではないんですね。
なぜなら防止法であって禁止法じゃないからです。
国の家族観は明治時代からほとんどアップデートされていないが、社会は急には変わらない。
そんな中でせめて自分が被害にあわないためには、「わがままになりましょう」と信田さんはメッセージを送ります。その真意とは?
選択肢を持って生きるために/選択的夫婦別姓・全国陳情アクション 井田奈穂さん

「夫婦同姓を法で強いる国は世界で日本だけ。諸外国から『人権後進国』と非難されても仕方ない状況」と指摘するのは、「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」で事務局長を務める井田奈穂さん。
選択的夫婦別姓に関しては、先日国連から、4回目となる導入を求める勧告が出ました。にも関わらずなかなか導入が進まない現状に対して、井田さんは「声を上げ続けなければ」と話します。
諸外国からすれば、「まさか夫婦同姓を強いている国がまだあったなんて」という状況なので、望まない改姓の問題は、国際社会から理解されづらい。
そのため、日本人が議員陳情や裁判を通して声をあげていかなければ、法改正は難しいのが現状です。
では、女性たちがたくさんの選択肢を持って生きられる未来をつくるために、女性たち自身ができることは何なのでしょうか。
男性が「女性を品評する」社会に苦しまないために/『ブスなんて言わないで』とあるアラ子さ
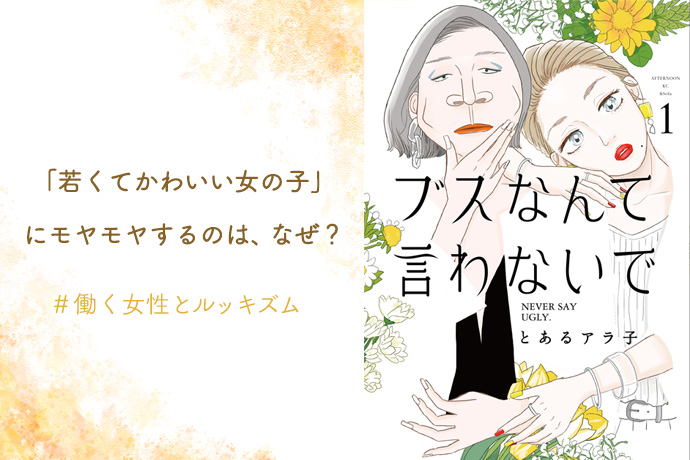
ルッキズムに正面から切り込み、大きな話題を呼んだ漫画『ブスなんて言わないで』の作者である、とあるアラ子さん。
ルッキズムの根本には、女性の地位の低さがあると指摘します。
難しいのが、ある日突然「女の人はきれいにしなくてもいいですよ」という法律ができたとしても、女性の大多数はきれいであることを手放せないと思うんですよね。
なぜかというと、「きれいでいなければ恥ずかしい」という気持ちが女性たちにあるから。
この恥じらいの正体を探っていくと、世の中が厳然たる男性社会であることに原因がある気がします。
男性優位の社会で、「弱い方の性別」である女性は見た目で差別を受けてしまうことがある。
その価値観を内面化してしまっているがために、女性たちはどうにかきれいになろうと思ってしまうわけじゃないですか。
ルッキズムの問題はすぐには解決できないけれど、小さな行動から変化を起こすことはできると話す、とあるさん。
とあるさんが語る、私たち個人でもできる行動とは。
職場でジェンダーギャップを感じたり、違和感を覚えたりすることがあった時、こうした小さな行動が大きな変化を生むかもしれません。
私たちが働き続ける未来を少しでも良くするためのヒントをくれる4人の女性たちのメッセージ。ぜひ参考にしてみてください。
文/Woman type編集部
















