
ハイブリッドワークに“見えない壁”? リモートでも評価される会社を見抜くポイントをキャリアのプロが徹底解説
20代~30代の女性が抱える仕事・キャリア・転職のお悩みに、その道のプロが本音でアドバイス! 「私らしい働き方」の発見や「いい転職」をかなえるためのヒントを提供します
今回、転職に関するお悩みに答えてくれたのは、「選択できる自分になる」ためのキャリア戦略を共につくるパートナー『キャリパト』を運営する株式会社Your Patronum 代表取締役、森数美保さん。
届いたのは、「リモートワークと出社のハイブリッドで、出社組が優遇されている気がする…」という女性からのお悩みです。
かつて300名以上のフルリモート組織を運営した経験を持つ森数さんに、女性がリモート環境でキャリアを築き、成長していくための思考法を教えてもらいました。

株式会社Your Patronum 代表取締役
森数美保さん
新卒で人材紹介会社ジェイ エイ シー リクルートメントに入社。最年少マネージャーを経験。大手企業で人事を経験した後、株式会社Misoca(現:弥生株式会社)などを経て、18年11月 株式会社キャスターに入社。21年4月 同社執行役員に就任し複数事業を管掌。22年5月株式会社ミライフに執行役員として入社。キャリアコンサルタント/人事/事業経営の経験を活かして、本質的なキャリア構築や組織づくりを推進。24年に株式会社Your Patronumを創業。社会保険労務士有資格者。
お悩み:結局、出社しないと評価されないの? ハイブリッドワークの“見えない格差”にモヤモヤ
週3回はリモートワークOKの会社にいます。会社で認められている制度なのに、結局は出社派が優遇されていて、キャリアへの影響や評価制度などに不安を感じることもあります。
リモートでもちゃんと成長できて、評価してくれて、給与も上がるような会社はどうすれば見つけられますか?
森数さんの回答:リモートワークと出社は「全く別のゲーム」
「リモートOKの会社なのに、出社派が優遇される気がする」という違和感、すごくよく分かります。
実は、リモートと出社は「働く」という点では同じでも、まったく違う“ゲーム”なんです。
例えるなら、サッカーとフットサルほどの違いがあります。ルールが似ているようで、求められるスキルや連携の仕方がまるで異なるのです。
私自身、全員フルリモート、出社/リモートハイブリッド(私は出社可能圏内)、出社/リモートハイブリッド(私は遠方フルリモート者)という三つのパターンすべてを経験してきました。
その中で感じるのは、「条件が揃っている」ことが、いかに組織運営を容易にするかということです。
特に「出社/リモートハイブリッド」のようにルールが混在する場合、難易度は一気に跳ね上がります。
出社している人にとっては当たり前に得られる情報、たとえば「たまたま耳に入る会話」「偶然の雑談」「非言語的な雰囲気」などは、リモートでは一切得られません。
しかもそれは、本人のスキルや意欲に関係なく、「そこにいないから」起こる現象なのです。
自分だけがリモート参加している会議の居心地の悪さや、出社組の雑談で何かが決まっていた……という体験は、多くの人が経験しているのではないでしょうか。

私が300名超のフルリモート組織を運営していた中で学んだのは、ハイブリッド組織においては、組織全体のルールをリモート基準に合わせることが、もっとも公平な土台を作る近道だということです。
たとえば会議であれば、出社組も一人一台PCからZoomに入り、音声は一つのマイクにまとめる。
また、Slackなどチャットツールの文化を整備し、「見えないからこそ反応する」「5分考えて分からなければ即聞く」といった、“空気を読む”のではなく、“意図的に発信する”コミュニケーションを推奨する。
こうした環境設計が、情報の非対称性を減らし、チームの心理的安全性を高めます。
出社が優遇されている(と感じる)ような状態が続くと、
・がんばっているのに伝わらない
・評価されていない気がする
・この会社でキャリアを築ける未来が見えない
といった気持ちが積み重なり、モチベーションや成長の機会を逃してしまう可能性もあります。
「このままでいいのかな」と思い始めた今は、自分のキャリアを見直すタイミングかもしれません。
リモートでもちゃんと評価される会社は「ゲームのルールが揃っているか」どうか

まずは、今の会社で同じような悩みを持つ仲間とチームを組み、少しずつ働きやすさを改善していくアプローチも検討してみてください。
ただし、環境や文化的にそれが難しい場合は、転職を視野に入れるのも一つの手段です。
では、「リモートでもちゃんと評価される会社」はどう選べばいいのでしょうか?
理想は、全員がリモート勤務の会社や、ハイブリッドであっても出社日や働き方が統一されている会社です。
そのうえで、以下の三つの視点を軸に面接で確認してみてください。
1.評価制度が“言語化”されているか?
・どんなプロセスで目標設定され、どう評価されるのか?
・チーム貢献やナレッジ共有は、評価に含まれているか?
・フィードバックの頻度や手法はどうなっているか?
評価制度が“なんとなく”ではなく、説明可能な仕組みとして運用されているかが大切です。
2.「リモート前提」の組織設計になっているか?
・会議、雑談、資料共有などがすべてオンラインでも機能する設計になっているか
・出社とリモートの温度差や情報格差に、どんな対策をしているか?
組織運営の前提が出社寄りだと、リモート勤務者はどうしても不利になります。
3.ノンバーバル(非言語的)コミュニケーションに依存しない文化があるか?
リモートで働く上での大敵は「察してほしい文化」です。
それを回避するために、以下のような文化が根づいているかを確認してみましょう。
・Slackで「今から確認します」「会議後に返信します」といった反応が当たり前になっている
・情報共有が必ずテキストで残される(会議ログ・決定事項など)
・質問への回答が、一定のテンポで返ってくる
「発信が評価される」「反応が返ってくる」文化がある会社は、心理的安全性が高く、リモートでも安心して働けます。
環境への違和感やモヤモヤは、甘えではない

相談者様が今感じている「見えない努力が報われない」「評価の起点がずれている気がする」といった違和感は、決して小さなものではありません。
それは甘えでも、気にしすぎでもなく、環境の“ルール設計”と“情報構造”にズレがあることによって生まれる、もっとも自然な感覚です。
しかもこのズレは、積み重なることで
・自己効力感の低下
・成長の実感の喪失
といった「見えないブレーキ」をかける原因になりかねません。
もし今、「このままでいいのかな」「ちゃんと見てもらえる場所で働きたい」と思えているのだとしたら、”キャリアを主体的に選ぼうとしている証”です。
心に浮かんだ違和感やモヤモヤを大切にし、自分にとって最適な働き方を見つけていけるよう、心から応援しています。
【書籍情報】「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略
森数さんの新著が好評発売中!
「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略
やりたいことがなくても選べる未来をつくる方法
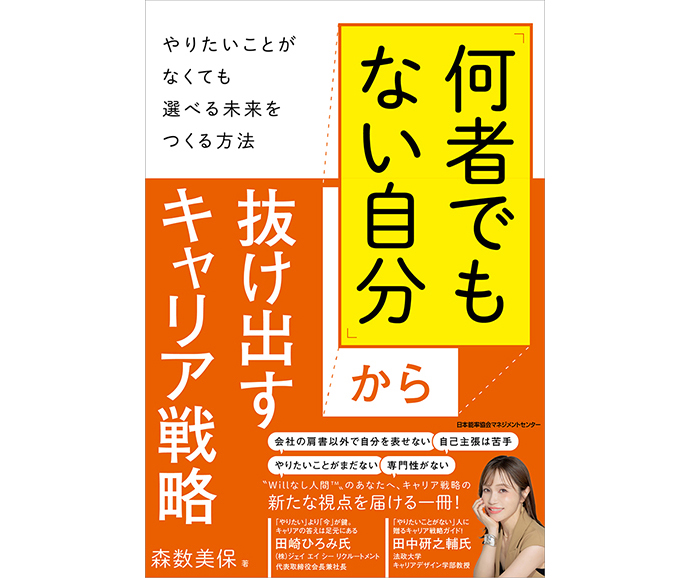
キャリアの「Will」がない、キャリア目標を作ることに苦しむ方に届けたい、やりたいことを見つけることを「前提としない」 キャリア戦略本!
『働く女性の転職Q&A』の過去記事一覧はこちら
>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/consultation/をクリック








