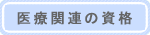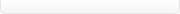- 女の転職トップ
- >
- 介護の仕事 女の転職typeトップ
- >
- スキルを活かす!介護・福祉の資格を活かした転職
- >
社会福祉士
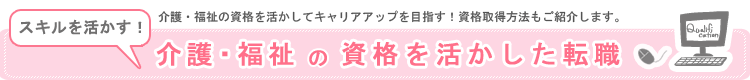
介護・医療・福祉に関する資格の種類や取得方法から、勉強方や難易度まで分かりやすく解説。
社会福祉士
心身に障害を持った人や、日常生活を営む上で支障のある高齢者など、福祉サービスを望む人たちの相談を受けて、適切な助言や指導、援助を行う専門職で、社会福祉業務に関わる者のための資格。
職域は広く、児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉、医療福祉など多方面に広がる。職場での職種名は、ソーシャルワーカー、メディカルソーシャルワーカー、相談員、指導員、相談指導員などさまざま。
現在資格がなければ業務に就けないと定められた職種や職場はないが、相談内容の深刻化・複雑化が進む今、社会福祉の中心的な役割を担う専門家として、社会福祉士の活躍に期待が高まっている。各種福祉施設や医療機関、行政機関など、有資格者を求める場は多く、採用要件とする求人も着実に増えている。
国家資格に合格しなければいけません。福祉系大学卒業後、すぐに受検するコースが一般的だが、福祉系の短期大学に進学し、1~2年の実務経験を積んだ上で試験に挑む方法もある。一般の大学を卒業した方は、社会福祉士の養成施設を修了することで受検資格が得られる。このほか、指定施設で4年以上の相談援助実務を経験した後、養成施設を修了して、受検資格を得ることも可能。養成施設には、昼間通学制(1年)、夜間通学制(2年)、通信制(1.5~2年)のコースがある。
学習内容
受検資格
社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学、医学一般、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、社会福祉援助技術及び介護概論など学習範囲が多岐に渡る試験。かたよりのない学習を心がけ、事例問題対策として、社会福祉に関わる専門雑誌や新聞に目を通し、最新の動向を押さえておくことが重要です。
※精神保健福祉の資格を持っている人は、申請をすると、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学、医学一般が免除される。
受検資格
大学等で「指定科目」を履修した方
社会福祉士「養成施設」を卒業した方
福祉事務所の査察指導員等の実務経験が5年以上ある方
| 難易度 | ★★★ |
| 合格率 | 30%程度 |
| 取得期間の目安 | 4年以上 |
主な職場
社会福祉に関する専門的な知識と技術をもって、福祉サービスを必要とする人の相談に応じ、アドバイスや指導などの援助を行うのが、社会福祉士の仕事。高齢者や障害者、児童やその家族を対象とし、相談・援助の専門家として、問題を解決へと導いていく。活躍の場は多方面に広がっており、「地域包括支援センター」には必ず有資格者を置かなければならない。



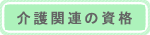

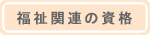
 社会福祉士
社会福祉士